| Weekly Collumn |
       |
| 丂 |
| VOL940丗暯惉28擭10寧31擔丗FPGA偭偰柌偼峀偑傝傑偡偹 |
仜僨僕僞儖夞楬嫵堢偑廔傢偭偨
丂僨僕僞儖夞楬偲儅僀僐儞偺島媊偑堦捠傝廔傢傝傑偟偨丅嵟屻偺嵟屻偵FPGA偺拞偵儅僀僐儞偲IO峔抸偟偰Verilog偲C偱惂屼偡傞偭偰偄偆搝偑偁偭偨偺偱偡偑丄偙傟偑巚偄偭偒傝擄暔偱偟偨丅偄傗丄儅僀僐儞偲IO傪峔抸偡傞偲偐偼寢峔妝偪傫偩偭偨偺偱偡偑丄愭惗偑屻敿偵岦偗偰媫懍偵壽戣偺擄堈搙傪忋偘偰偄偔偺偱丄側傫偣傎偲傫偳扤傕偮偄偰偙傟側偄偲偄偆崜偄偁傝偝傑偱偟偨丅偪側傒偵FPGA偼ALTERA偺Cyclone3丄撪晹偵嶌傞CPU偼Nios2/e偱丄壽戣偲偄偆偺偑乽傾儔乕儉婡擻偺偁傞帪寁傪嶌傟乿偱偟偨丅傑偁偝偡偑偵1偐傜嶌偭偰1擔偱傗傟偭偰偺偼柍棟側偺偱愭惗偑偁傞掱搙梡堄偟偰偔傟偰偼偄偨偺偱寢峔傑偩儅僔偩偭偨偺偱偡偑偹偊丅巹偑堷偭偐偐偭偨偺偼乽墴偟儃僞儞偺僠儍僞儕儞僌傪Verilog偺夞楬偱杊巭偡傞乿偲偄偆偲偙傠偱偟偨丅僋儘僢僋偲僔僼僩儗僕僗僞傪棙梡偟偨傾儞僠僠儍僞儕儞僌夞楬傪嫵杮捠傝偵慻傫偱傕夞楬撪偱慡偔婡擻偣偢丄偙偺傾儞僠僠儍僞儕儞僌傪奜偡偲慡婡擻偑偪傖傫偲摦偄偨偺偱丄嵟廔揑偵愭惗偺巜帵偲偼奜傟傞偺偱偡偑傾儞僠僠儍僞儕儞僌傪C尵岅懁偱惂屼偟丄墴偟儃僞儞偺IO偼晛捠偵慺捠偟偱CPU偺IO偵棳偟崬傓晽偵曄偊偰摦偐偟傑偟偨丅偪側傒偵壠偵栠偭偰偒偰偐傜帺暘偱峸擖偟偨DE0儃乕僪偱傗偭偨傜偪傖傫偲傾儞僠僠儍僞儕儞僌夞楬偑摦嶌偟偨偺偱丄懡暘偁傟偼儃乕僪懁偵傕側傫偐偁傞傫偠傖側偄偐丄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂
仜FPGA偲Nios2
丂偱丄偙偺Nios2偱偡偑丄FPGA偺拞偵峔抸偡傞偺偱偡偑寢峔彫婯柾側夞楬偱峔惉偝傟偰偄傞傛偆偱丄桳椏斉偱晜摦彫悢揰墘嶼傪弌棃傞僞僀僾偺CPU傪慻傒崬傫偱傕Cyclone3偲偄偆斾妑揑僲乕僪悢偺彮側偄FPGA偱傕4妱掱搙偟偐撪晹峔惉傪棙梡偟傑偣傫丅偙傟偵怓乆側IO傪捛壛偟偰傕僲乕僪悢帺懱偵偼梋桾偑偁傝傑偟偨丅傑偨丄偙偄偮偑曋棙側1偮偑僞僀儅乕傪暋悢峔惉弌棃傞偙偲傗丄峔惉偡傞IO偵偼帺暘偱柤慜偲儊儌儕斣抧傪愝掕偱偒傞偙偲丄儗僕僗僞偲偄偆奣擮偑偳偆傕側偄廘偔偰愱梡偺C偱偟偐埖偊側偄戙傢傝偵IO傪扏偔偺偵IO柤偺億僀儞僞偱屇傃弌偣偽僨乕僞偺撉傒彂偒偑偱偒傞偙偲丄側偳側偳偺偍庤寉側柺偑偁傝傑偡丅晛捠偺儅僀僐儞傪C偱巊偭偰IO扏偙偆偲巚偆偲暿偵IO柤偲IO偺傾僪儗僗傪昍晅偝偣傞儅僋儘傪偟偙偨傑彂偒崬傫偩僿僢僟僼傽僀儖傪梡堄偟側偄偲僟儊偱偡偐傜偹丅偨偩偟愱梡偺C偑寢峔暼偑偁偭偰丄椺偊偽pritnf側偳偼alt_printf偲側傞忋偵%d偑巊偊側偄偲偐丄傑偁傎偐偵傕怓乆偲懡彮偺惂尷偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偦偺婥偵側傟偽僴乕僪峔惉傕堦弿偵偑偽偭偲曄偊傜傟傞偲偐丄IO扏偔偨傔偺僿僢僟傪慡晹愱梡偺C尵岅婰弎僜僼僩偑梡堄偟偰偔傟傞偲偐偼曋棙側偺偱丄崱屻傕偣偭偐偔庤偵擖傟偨DE0儃乕僪傕偁傞偺偱怓乆梀傫偱傒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅12000墌偱偙傟偩偗梀傋傞僆儌僠儍偭偰憗乆側偄偱偡傛丅
丂
仜媣乆8偺帤僋儖僋儖
丂9寧偵僞僀儎傪PilotRoad2偵棜偒懼偊偰偐傜弶傔偰僷僀儘儞偔傞偔傞偟偵峴偒傑偟偨丅弮惓憰拝偺D222偺帪偼偁傗傆傗側愙抧姶傗僿儞僥僐側僴儞僪儕儞僌偑寢峔傾儗偩偭偨偺偱偡偑丄PR2偼搢偟偙傒偑旕忢偵寉偔幵懱偺僶儞僋検傕捦傒傗偡偄偺偱丄寢峔娙扨偵僋儖僋儖弌棃傞姶偠偱偡丅傑偨丄崱傑偱壗搙傕棜偄偰偒偨僞僀儎偩偗偵怣棅姶傕偁傞偺偱丄僽儗乕僉儞僌偱僒僗墴偟崬傫偱偦偺傑傑偖偄偭偲岦偒傪曄偊偰僋儕僢僺儞僌偵偮偄偰傑偭偡偖扙弌偑偟傗偡偔側偭偰偄傑偡丅偱丄偦偺寢壥偼摦夋傪尒偰傕堦栚椖慠偱偟偨丅D222偺帪偼偦傕偦傕棫偪忋偑傝偱僷僀儘儞懁偵婑偣傞偺偑寢峔戝曄偩偭偨偺偱偡偑丄PR2偵棜偒懼偊偰偐傜偼寢峔偡偭偲婑偣傜傟傑偡丅婑偣傜傟偡偓偰偙偺擔偺楙廗偱偼壗搙偐泺偱僷僀儘儞傪堷偭妡偗偰僘僓乕偝偣偰偟傑偭偰偄傑偟偨丅偨偩憡曄傢傜偢塃偑嬯庤側偺偼偦偺傑傑傒偨偄偱偡丅嵍夞傝偩偲僷僀儘儞偼偳偭偪偐偲偄偆偲椬偺僷僀儘儞偺傎偆傊岦偐偭偰棳傟偰偄偔偺偱偡偑丄塃夞傝偩偲奜懁偵岦偐偭偰棳傟偰偄傑偡丅偮傑傝丄嵍偼泺偑堷偭偐偐傞帪揰偱曽岦揮姺偑傎傏廔傢偭偰傞傫偱偡偑丄塃偼偪傚偆偳僋儕僢僺儞僌偺恀墶偵幵懱偑棃偨帪偵堷偭妡偗偰傞姶偠偱偡丅嵍偲堘偭偰塃偼偳偙偱夞傝巒傔偰偄偄偺偐傛偔傢偐傜側偄偭偰偺偑幚忣側偺偱丄傕偆偪傚偭偲楙廗偟側偄偲僟儊偱偡偹丅
丂
仜媣乆屼庨報2儁僞攓椞
丂擔梛偼僜儘僣乕偱攄廈偺恄幮弰楃偺椃偵弌偰偄傑偟偨丅尦乆僜儘偱憱傞偺偵偳偙傪憱傠偆偭偰偲偙傠偐傜僱僞偑巒傑偭偰偄偰丄摉擔偺揤婥攝抲側偳傕峫偊偨偲偙傠傗偭傁惣偐撿偲側傝傑偟偰丄挿傜偔憱偭偰側偄暫屔導摴8崋慄偺偨傃偵偟傑偟偨丅傑偁柍棟偟偰傕巇曽偑側偄偺偱慜敿偺扥攇僄儕傾偼僔儑乕僩僇僢僩偱偡偭旘偽偟偰桳攏宱桼偱幮IC偐傜惣榚偵敳偗傞僐乕僗偱偄偒傑偟偨丅幚偼偙偺儖乕僩傪憱傞偺偼5擭傇傝偔傜偄3夞栚偩偭偨偺傕偁偭偰悘暘摴傪朰傟偰偄偰丄変側偑傜憱偭偰側偄側乕偲丅偙偺儖乕僩偱堦斣妝偟偄偺偼曯嶳崅尨偵忋偑傞摴偱偡偹丅TDM900傗MT-09 tracer偵偼偆偭偰偮偗偺僐乕僗側斀柺丄儕僢僞乕SS偲偐偵偼偪傚偭偲恏偄応強偱偡丅偱丄偙傟偱幊埦堦媨偵弌偰埳榓戝幮偵偍嶲傝偟丄崱夞偺庡栚揑偱偁傞棻嵖揤徠乮偮傇偵傑偡偁傑偰傜偡乯恄幮偲拞恇報払乮側偐偲傒偄偩偰乯恄幮偺2偮偺墑婌幃偺幃撪幮偵偍嶲傝偟丄屼庨報傪捀偒傑偟偨丅幚偼傕偆1幮偡偖偦偽偵椬愙偟偰偁傞傫偱偡偑丄偙偪傜偼媨巌偝傫偼挬梉偲嵳釰埶棅偺帪埲奜偼棃傜傟側偄偲偺偙偲偱丄屼庨報攓椞傪抐擮偟傑偟偨丅側傫偮乕偐偪傖傫偲晹壆傪枅廡憒彍偟傛偆両偲偐丄偪傖傫偲弰楃傪傗傠偆両偲偐丄偦偆偄偆堄巚偑傗偭偲偙偝栠偭偰偒偨偺偼戝偒偄偱偡偹丅 |
| VOL939丗暯惉28擭10寧24擔丗旘墠傪尒偰偒偨 |
仜嶰幃愴乽旘墠乿
丂yui巓偝傫偑婣徣偺偮偄偱偵娭惣偵傛偭偰梀傫偱偄偔偲偄偆偺偱丄偮偄偱側傫偱僇儚僒僉儚乕儖僪偲旘墠偺摿暿揥帵偵峴偭偰偒傑偟偨丅僇儚僒僉儚乕儖僪偼恖偑棃傞偨傃偵楢傟偰偭偰傞偺偱摿偵栚怴偟偄儌僲偼偁傝傑偣傫偱偟偨偑丄揥帵暔偵H2偲H2R偑憹偊偰偄傑偟偨丅偁偲丄僇儚僒僉偼傗偼傝揥帵偑忋庤偱偡偹丅偪傖傫偲幵懱偺壓偵嬀偑愝抲偟偰偁偭偰奆偑婥偵側傞幵懱壓晹偑偪傖傫偲尒偊傞傛偆偵偟偰偁傝傑偟偨丅偱丄偦偙偐傜億乕僩僞乕儈僫儖偵堏摦偟偰嶰幃愴旘墠偺摿暿揥帵傪尒偵峴偒傑偟偨丅揥帵偝傟偰偄偨偺偼帋嶌17崋婡偱尦乆抦棗偵抲偄偰偁偭偨傗偮丅尰抧偵偮偄偰旘墠偺慜偵戝堥巵偲3恖暲傫偱棫偭偨搑抂偵栚偺慜偵廋暅僠乕儉儕乕僟乕偑尰傟偰僾儘僕僃僋僩偺愢柧偑巒傑傞偲偄偆挻儔僢僉乕側忬嫷偺拞偱尒妛僗僞乕僩丅杮摉偵傛偔廋暅偝傟偰偄傑偟偨丅椺偊偽偱偡偑丄帋嶌17崋婡偼僗乕僷乕僠儍乕僕儍乕偑幐傢傟偰偄偨偺偱偡偑丄偦傟傪僴40偺尨宆偲側偭偨DB601偵晅偄偰偄偨僠儍乕僕儍乕傪尦偵儕僾儘偟偨偦偆偱偡丅傑偨丄婡庬婡娭朇偺僇僶乕偵傕側偭偰偄傞僄儞僕儞忋晹僇僶乕側偳傕儕僾儘偝傟偰偄偨傝丄抦棗偵揥帵偺嵺偵帺徧愱栧壠側偨偩偺儅僯傾偑彑庤側壇應偲峫徹偱傗偭偪傖偭偨廋暅偲偄偆柤偺杺夵憿晹暘傪尨宆偵栠偡嶌嬈傪悘暘峴偭偨偦偆偱偡丅傑偨丄儕乕僟乕偝傫偵捈愙幙栤偡傞僠儍儞僗傕偁偭偨偺偱暦偄偰傒偨偺偱偡偑丄17崋婡偼岾偄寘傪愗傜傟偰偄傞晹暘偑側偐偭偨偦偆偱丄惓偟偄婡懱悺朄傗僼儗乕儉悺朄偺寁應傕峴偊偨偦偆偱偡丅僄儞僕儞傕堦搙慡夝懱偟偰慻傒側偍偟偰偁傞偦偆側偺偱偡偑丄偙傟傪婡偵僼儔僀傾僽儖側儗僾儕僇傪嶌偭偰偔傟偨傜側偀丄偲偐巚偭偨傝巚傢側偐偭偨傝丅
丂
 丂 丂
丂嶰幃愴偺尒妛偱偦偆偄傗傗偭傁傝巹傕婥偵側偭偨揰偼婡懱壓晹偵愝抲偡傞儔僕僄乕僄僞乕仌僆僀儖僋乕儔乕偱偟偨丅偙傟偼怓乆側僒僀僩傗帒椏偱傕偙偺椻媝憰抲偼僪儃儞揰偺1偮偩偭偨偲偁傝傑偟偨偑丄幚暔傪尒偰妋偐偵乽偙傝傖乕楻傟傞偟椻偊傫傢乿偲巚偄傑偟偨丅傑偢僐傾偺峔憿偱偡偑丄僴僯僇儉宍忬偺摵娗傪愊傒忋偘偰偼傫偩晅偗偟偰偁傞偺偱偡偑丄棳懱偑捠傞寗娫偑偐側傝彮側偔丄僐傾僒僀僘偵懳偟偰柧傜偐偵椻媝婡擻偼懌傝側偄偩傠偆偲偄偆姶偠偱偟偨丅傑偨丄偙傟傕奺庬帒椏捠傝3偮偵暘偐傟偨僐傾偺偆偪丄嵍塃椉懁偑椻媝悈偱拞墰偑僆僀儖僋乕儔乕側偺偱偡偑丄堦懱偱嶌偭偪傖偭偰傞偺偱悈偲僆僀儖偺壏搙嵎偱榗傓偩傠偆側偁偲偄偆姶偠偱偡丅儔僕僄乕僞乕偺埵抲帺懱偼幚偼暷孯偺P-51儅僗僞儞僌偲摨偠埵抲偵偁偭偨傝偡傞傫偱偡偑丄柧傜偐偵儔僕僄乕僞乕杮懱傗摫晽偺峔憿丄惍旛惈傪峫椂偟偨搵嵹曽朄側偳慡慠堘偭偰偄偨偦偆偱偡丅旘墠偺惍旛偱偼椻媝婍偺拝扙偑戝曄偩偭偨偲偁傝傑偡偑丄妋偐偵廋暅夁掱偱偺搵嵹僥僗僩側偳偺幨恀傗塮憸傪尒偰傞偲丄偙傝傖乕愴抧偱惍旛偟偨偔側偄側偭偰姶偠偱偟偨丅傑偨丄儔僕僄乕僞乕偺峔憿偵偮偄偰偼Wikipedia偱偼乽慜偐傜弴偵悈亜僆僀儖亜悈乿偭偰彂偄偰偄傑偡偑丄幚暔偼乽嵍塃椉懁偑悈偱拞墰偑僆僀儖乿偱偡丅
丂
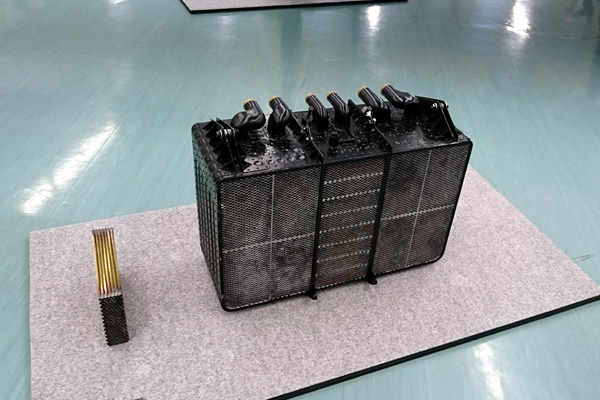
丂
仜朸幮揹抮偑敋敪偟傑偔偭偰傞審
丂擔杮恖偭偰傎傫偲傾儂偩偐傜徴寕揑側摦夋偑弌棃偰偨傜慡晹摨偠偩偲巚偄崬傓偭偰丄傎傫偲傾儂偩側偀偭偰巚偄側偑傜偙偺堦審傪尒偰偄傑偟偨丅僱僢僩忋偵崱榖戣偺朸幮偺実懷偵搵嵹偝傟偰偄傞揹抮傪庢傝弌偟偰僴儞儅乕偱壗搙傕僪僣偄偨傜敪壩敋敪偡傞偲偄偆偺偑偁傝傑偟偨丅巹偼偁偺摦夋傪尒偰乽偁傟丠偍偐偟偄偧丠乿偲婥偯偄偨傢偗偱偡丅傾儊儕僇偱斕攧偡傞偨傔偵偼傾儊儕僇偺儕僠僂儉僀僆儞揹抮偺埨慡婎弨傪枮偨偝側偄偲懯栚偱偡丅偦偺拞偵乽徴寕傪梌偊偰傕敪壩偟側偄乿乽屲悺揃偱懪偪敳偄偰傕敪壩偟側偄乿乽愜傝嬋偘偰傕敪壩偟側偄乿揑側儌僲偑偁傝傑偡丅嶐崱丄揹埑偑4.0V傑偱偵側傞偺偵崅揹埑傪昁梫偲偟側偄応崌偼偁偊偰惓嬌偵揝僆儕價儞偑嵦梡偝傟傞椺偑懡偄偺偼傑偝偵偙偺曈偺懳嶔偩偭偨傝偟傑偡丅崱夞偺朸幮偺揹抮偼晧嬌偵SiC偑巊傢傟偰偄傑偡丅SiC晧嬌偼崟墧晧嬌傗妶惈扽晧嬌偲斾傋丄儕僠僂儉傪僪乕僾偱偒傞検偑戝暆偵懡偄斀柺丄儕僠僂儉傪僪乕僾偡傞偲戝暆偵懱愊偑憹偊傞偨傔丄廩曻揹傪孞傝曉偡偲棻巕偑妱傟偰梕検偑戝暆偵楎壔偡傞偲偄偆庛揰偑偁傝傑偟偨丅崱夞嵦梡偝傟偨偺偼愭擔僾儗僗儕儕乕僗偺偁偭偨TDP奐敪偺怴宆僶僀儞僟乕傪棙梡偟偨傫偩偲巚偭偰偄傞偺偱偡偑丄偙偺SiC晧嬌嵽丄傕偆1偮擄揰偑偁偭偨傝偟傑偡丅偦傟偼丄儕僠僂儉偑僪乕僾偝傟偰崅妶惈忬懺偩偲娙扨偵栆楏側惃偄偱敪壩偡傞偲偄偆偙偲偱偡丅崱夞偺敪壩帠屘偱偼CT塮憸偱実懷揹榖偺鉃懱撪偱愊憌儔儈僱乕僩僙儖偑埑敆偝傟丄晹暘揑偵曄宍偑惗偠偰偄傞偙偲偑妋擣偱偒偰偄傑偡丅偙偺曄宍晹暘偐傜儔儈僱乕僩奜憰偵僩儔僽儖偑敪惗偟偰奜婥偑擖傝崬傒丄SiC晧嬌嵽偑嬻婥拞偺拏慺偲悈暘偲愙怗偟丄Li-N惗惉斀墳偱敪擬仌悈慺惗惉丄敪擬偱悈慺偵拝壩丄偦偺擬偱揹夝塼偺EC傗MEC偑堷壩偟墛忋偟偨傫偠傖側偄偱偡偐偹丅傑偨丄徚壩帪偵悈傪傇偭偐偗偰敋敪偝偣偨椺傕偁傞偐偲巚偭偰偄傑偡丅傑偁偡傋偰偼壇應偱偟偐側偄偺偱偡偑丄揹抮偺尰応傪棧傟偰敿擭埲忋偱偡偑丄偙傟偔傜偄偼娙扨偵梊憐偑偮偄偨偭偰偍榖偱偟偨丅 |
| VOL938丗暯惉28擭10寧17擔丗C尵岅丄側傫偲側偔暘偐偭偰偒偨 |
仜C尵岅偭偰寢峔敾傝傗偡偄
丂C尵岅廗偭偰戝懱7擔栚偔傜偄丅幚偼偁偲偼嫟梡懱偲偐廗偭偨傜婎慴C島嵗廔傢偭偪傖偄傑偡丅偼偊偉乧乧丅偱傕惓捈側偲偙傠丄verillog傗傾僙儞僽儕傛傝傕埑搢揑偵敾傝傗偡偔捈姶揑偱丄傗傝偨偄偙偲傪僀儊乕僕偟偰峔憿傪峫偊偨傜偦偺捠傝偵婰弎偡傟偽OK両傒偨偄側姶偠偱偡偹丅枹偩偵偪傚偭偲鏣偄偰傞偺偑億僀儞僞偑棈傫偩娭悢偱偡丅偄傗傑偁億僀儞僞偱娭悢偵攝楍傪曻傝搳偘傞偲偙傠傑偱偼忋庤偔峴偔傫偱偡偑丄僾儘僩僞僀僾愰尵偲娭悢偺宆愰尵丄娭悢偵憲傝弌偡僨乕僞宆偺愰尵傪慡晹摑堦偟側偄偲庴偗庢偭偨愭偺張棟偱僘僢僐働傞偲偄偆傾儗偵偼傑偭偰偄傑偟偨丅偦偺曈偵偮偄偰偼twitter側偳偱儃儎偄偰偄偨傜巇帠偱C巊偭偰傞恖偨偪偐傜乽娭悢帺懱傪偦傕偦傕void宆偱愰尵偟偨傜偊乕偹傫丄void 娭悢柤(void)偱傕捠傞偱乿傒偨偄側姶偠偱偟偨丅側偍娭悢懁偱偪傖傫偲愰尵偟側偄偲傾僂僩傒偨偄偱偡偑丅傑偨丄twitter偱MAX僐乕僸乕偺僱僞偐傜MIN偩偺AVG偩偺偄偆榖偑弌偰偒偨偺偱丄乽擖椡偝傟偨10梫慺偺揰悢僨乕僞偐傜嵟戝抣丄嵟彫抣丄暯嬒抣傪媮傔傞乿偲偄偆僗僋儕僾僩傪悓偭暐偭偨忬懺偱15暘偔傜偄偱慻傫偠傖偭偨偺偱偡偑丄偙傟傕偦偺傑傑twitter傗mixi偱揧嶍偟偰傕傜偭偨傝丅嵟廔揑偵偙傟偱摦偔傫偠傖偹丠傒偨偄側姶偠傑偱慻傔偨偺偱僐儞僷僀儖偟偰憱傜偣偨傜巚偭偨捠傝偺摦偒偵偼側偭偰偄傑偟偨丅偄傗乕丄暘偐偭偰偔傞偲C偭偰儂儞僩柺敀偄偱偡偹丅C偑暘偐傞偲Java傗儔僘僷僀丄Arudino偵傕揥奐偱偒傞偭偰榖側偺偱丄C偺扨尦偼婥崌擖傟偰婃挘偭偰偄偒偨偄偱偡偹丅
丂
仜弶怱幰嫵摫僣乕偵峴偭偰偒偨
丂僶僀僋壆偺師彈19嵨偑儘乕僪僣乕儕儞僌僨價儏乕偱傎偐偵庒幰側偳弶怱幰傪壗恖偐楢傟偰峴偔偲偄偆偺偱丄揦挿1柤偩偗偱偼僣儔偦偆側偺偱僒億乕僩栶偲偟偰嶲壛偟偰偒傑偟偨丅傎偐偵偁偲2柤儀僥儔儞偑僒億乕僩栶偵夞偭偰偔傟偨偺偱慡懱揑偵妝偵僒億乕僩偱偒傑偟偨偹乕丅僣乕儕儞僌偭偰巹偼弶怱幰偺偙傠偼晅偄偰偄偔偲姰慡偵抲偄偰偗傏傝偵偝傟傞偩偗偱偟偨丅偩偐傜寵偱傕昁巰偱摴傪妎偊傑偟偨偟丄妎偊偨摴偼朰傟側偄傛偆偵偟傑偟偨偟丄憱傝巒傔傞慜偵戝傑偐側儖乕僩傕忢偵妋擣偟偰偄傑偟偨丅偱傕偹偊丄偦傟偑寵偱儅僗僣乕偵棃側偔側傞恖偑杮摉偵懡偐偭偨偺偱丄巹偼帺暘偑儀僥儔儞偵側偭偨傜嫵摫偼偪傖傫偲傗傠偆偲巚偭偰偄傑偟偨丅偱丄30戜傕敿偽偵側偭偨傜嫵摫僣乕偑偁傟偽愊嬌揑偵嫵偊傞懁偱夞偭偰偄傑偡丅崱夞偼庒偄巕2柤偼寢峔僉價僉價憱偭偰偔傟偨偺偱揦挿娵搳偘偱偟偨偑丄僐儉僗儊19嵨偑偳偆傕抶傟婥枴偩偭偨偺偱丄儀僥儔儞惃偱偑偭偪傝僒億乕僩偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅帠慜偵偙傟偑梊憐偱偒偰偄偨偺偱幵鏿傕摉慠TT-R偱偟偨偺偱僗僩儗僗傕側偟丅偝傜偵儕僢僞乕32噏偲偄偆擱旓偺僶僢働儞儗僐乕僪傕払惉偱偒偨偺偱寢峔枮懌偱偟偨丅傑偁丄搑拞偱乽偊丠偦偺堦尵偑尨場偱偦傫側宍偱偦傫側尵偄曽偱愨墢愰尵偡傞偺丠乿偲偄偆戝恖偘側偄堦審傕偁傝傑偟偨偺偱丄崱屻傕儊僀儞偺儘乕僪僣乕儕儞僌傗堸傒夛偼堦愗晄嶲壛偲偄偆偙偲偱丅
丂
仜NEX-C3偱壴嶣傝
丂偄偮傕偺晲屔愳壨愳晘偱偦傠偦傠偐偲巚偭偰僐僗儌僗傪嶣傝偵峴偭偨偺偱偡偑丄傑偩帪婜偑憗偐偭偨傛偆偱偁傑傝嶇偄偰傑偣傫偱偟偨丅偱傑偁榬姷傜偟傕偐偹偰36枃嶣傝1杮偲NEX-C3偱偦傟側傝偵嶣偭偰偒偨傫偱偡偑丄NEX偱嶣偭偨僇僢僩偼50枃偔傜偄嶣塭偟偰傾僞儕1枃偲偄偆懱偨傜偔偱偟偨丅偱丄幚嵺偵嶣偭偰偰巚偭偨偺偱偡偑丄D-SLR偱MF儗儞僘偟偐晅偄偰側偄峣傝崬傒應岝丄偟偐傕業弌曄峏偺儊僯儏乕偑惁偔巊偄偯傜偄NEX-C3偩偲丄抜奒業弌側偳傪峫偊傞偲偮偄僐儅悢偑憹偊偰偟傑偆傫偩側偀偭偰偙偲偱偟偨丅偁偲丄偦偺応偱僾儗價儏乕偑尒偊傞偺傕偁傞偐傜丄嶣傟偨僇僢僩偺壴偺岦偒偺椙偟埆偟偱偦偺応偱嶣傝側偍偟偪傖偆偭偰偺傕偁傝傑偡丅偦傝傖乕僇僢僩悢憹偊傞傛偭偰丅側偍傾僈儕傪尒偰偄傞偲傗偼傝嬧墫偱偄偄儗儞僘偑NEX-C3偱傕偄偄儗儞僘偩偲偼尷傜側偄偲偄偆姶偠偱偟偨丅椺偊偽丄廃曈偑攈庤偵棳傟偰偪傚偭偲儃働偑烼摡偟偄COSINA19-35mm偱偡偑偙偄偮偼NEX-C3偲憡惈偑椙偔偰鉟楉偵儃働偑弌偰丄嬧墫偩偲F1.7傛傝埖偄傗偡偄偲掕斣偺MD85/2偼嬧墫傛傝傕攚宨偺擇慄儃働孹岦偑攈庤偵弌偰巊偄偯傜偄儗儞僘偵側偭偰偄傑偡丅傑偨丄偳偺戝岥宎儗儞僘偱傕偄偊傞偙偲側傫偱偡偑丄巊偊傞ISO姶搙偑嵟掅偱200偱崅傔乮兛-7Digital偼100傑偱丄PowerShotG9偼80傑偱棊偲偣傞乯偱僔儍僢僞乕懍搙偑懍傔偵側傝偑偪側偺偵1/750s傪挻偊傞偲僪傾儞僟乕偱巊偄暔偵側傜側偄側傫偰戝寠傕偁傝傑偡丅
丂
仜寢嬊偁偲3杮傕揾傝捈偟
丂偙偺娫揾傝側偍偟偨傾儖儈儂僀乕儖傪壓偵帩偭偰崀傝偨偺偱偡偑丄傎偐偺3杮偲暲傋偨傜柧傜偐偵堘偄偡偓偰丄乽偙傝傖乕栚棫偮側偁乿偲梡帠偱僂僠偵棃偰偨備偢孨偲2恖偱榖偟偰傑偟偨丅傗偭傁傝偁傑傝偵傕僉儗僀偝偑堘偆傫偱偡傛偹丅偱丄傑偢偼慜椫偵壖偵晅偗偰傞2杮傪奜偝側偄偲懯栚側偺偱偡偑丄偁偄偵偔僼儘傾僕儍僢僉偼攋懝偟偰偐傜壗擭傕巇擖傟偰傑偣傫丅巇曽偑側偄偺偱僗僩儗乕僩偱巇擖傟偰偒傑偟偨丅傑偨丄埲慜偵儈僘僯乕儔儞僪偐傜忳偭偰傕傜偭偨傾僗僩儘偺僀儞僷僋僩偲慻傒崌傢偣偰嶌嬈偟偨偲偙傠丄埲慜偵僷儞僞亄廫帤儗儞僠偱傗偭偨偺偵斾傋偰1/3偺嶌嬈帪娫偱廔椆偟傑偟偨丅奜偟偨儂僀乕儖傪娷傔偰3杮偺儂僀乕儖偼僶僀僋壆偱價乕僪僽儗乕僇乕傪庁傝偰價乕僪傪棊偲偟丄僞僀儎儗僶乕偲僾儔僴儞偱庤嶌嬈偱僞僀儎傪堷偭傌偑偟偰偟傑偄丄儂僀乕儖偩偗偵偟偰偐傜僈儕彎偺曗廋傪偟偰偄傑偡丅偲傝偁偊偢偙傃傝偮偄偨僽儗乕僉僟僗僩傪慡晹愻嵻偱愻偄棊偲偟丄偮偄偨僈儕彎傪堦扷嬒偟偰偐傜僷僥傪撍偭崬傓偮偙傠傑偱廔椆偟偰偄傑偡丅偙偺屻偪傖傫偲姡偄偨僷僥傪嶍偭偰柺傪弌偟偨傜曗廋晹暘偵僒僼揾偭偰僂儗僞儞揾憰偱偡偹丅崱夞偼僒僼偼嵟掅尷偵嵪傑偣傞曽岦偱偡丅 |
| VOL937丗暯惉28擭10寧10擔丗寧梛擔偺乧乧 |
丂杮棃僸儞僰乕嫵搆偱偡偑寧梛偺偨傢傢偺傾僯儊偼僒僾儔僀僘偡偓傑偡傛丅偦偟偰曇傒崬傒偪傖傫偙偲傾僀偪傖傫偼摦偄偰惡偑摉偨傞偲壜垽偄両屄恖揑偵偼枀偪傖傫偺傎偆偑岲傒側傫偱偡偑偹丅
仜傾僙儞僽儕偺孭楙偑廔傢偭偨
丂孭楙峑偺傾僙儞僽儕偺孭楙偑廔傢傝傑偟偨丅妋擣壽戣偲偟偰弌偝傟偨偺偑埲壓偺撪梕偱偡丅
丂1丏8楢dip僗僀僢僠A丄B丄2偮偺僗僀僢僠偺擖椡傪悢抣壔偟丄僾僢僔儏僗僀僢僠4偮偵掕媊偝傟偨巐懃寁嶼傪偡傞丅
丂2丏摼傜傟偨寁嶼寢壥偺偆偪惓偺抣偩偗D3乣D10偺8屄偺LED偵2恑悢偱昞帵偡傞乮D3偑LSB乯丅
丂3丏dip僗僀僢僠偼ON偵側偭偨僗僀僢僠斣崋傪悢抣偲偟丄2偮埲忋憖嶌偝傟偰偄傞応崌偼0偲偡傞丅
丂4丏儃僞儞4偮偵掕媊偝傟傞巐懃偼儃僞儞愭摢偐傜弴偵壛嶼丄尭嶻丄忔嶼丄彍嶼偲偡傞丅
丂5丏寢壥偺昞帵偼僾僢僔儏僗僀僢僠憖嶌拞偺傒峴傢傟傞偙偲丅
丂6丏dip僗僀僢僠擖椡偺悢抣曄姺偼傾僙儞僽儕偱峴偆偙偲丅
丂7丏FPGA丄傾僙儞僽儕偲傕偵撪晹僼儔僢僔儏ROM傊彂偒崬傒儃乕僪扨撈偱嬱摦偡傞傛偆偵偡傞偙偲丅
丂
丂偲偄偆傕偺偱偟偨丅6帪娫偱傗傟偲偄偆壽戣偱偟偨偑巹偼偞偭偔傝3帪娫敿偱廔傢傝傑偟偨丅傑偢昁梫側張棟偺弴斣傪慡晹巻偵彂偒弌偟偰偄偒丄棳傟偺帪宯楍偱弴斣偵偟傑偡丅師偵偦偺彂偒弌偟偨儌僲傪僾儘僌儔儉峔憿偵増偭偰惔彂丅I/O儅僢僾傪暿偵梡堄偡傞偺偱崱夞巊偆I/O娭學偺儗僕僗僞傪巇條彂偐傜彂偒弌偟偰儅僢僾僼傽僀儖偵婰弎偟丄偦偙傑偱傗偭偰偐傜僾儘僌儔儉杮懱傪彂偒傑偟偨丅FPGA偵娭偟偰偼巜帵偑偁傞偺偱偍偲側偟偔擖弌椡僨乕僞傪庴偗搉偟偡傞偩偗偵偟偰偁傝傑偡偑丄dip僗僀僢僠偲push僗僀僢僠偑晧榑棟側偺偱丄偙偙偼FPGA偱not傪擖傟偰惓榑棟偵偟傑偟偨丅惓捈丄僨僐乕僟乕側傫偰FPGA偱傗偭偪傖偆偲case暥堦敪偱娙扨偵廔傢偭偪傖偆偺偱傔偪傖偔偪傖妝側偺偱偡偑丄傾僙儞僽儕偩偲CMP偐TST偱斾妑偟偰PSW偺僼儔僌尒偰忦審暘婒偟側偄偲偩傔側偺偱丄柺搢偔偝偄偭偨傜偁傝傖偟側偄丅3.5帪娫偺偆偪偔傜偄偼偙偺擖椡偵懳偡傞撪晹僨乕僞偺妋擣偲偺暘婒僼儔僌偺怘傢傟傑偟偨丅傾僙儞僽儕偼幚嵺偺揹巕夞楬僄儞僕僯傾偺悽奅偱偼夁嫀偺堚暔偲側傝偮偮偁傞偦偆偱偡丅C傊偺慻傒崬傒偡傜傎偲傫偳側偔丄CPU偺摿掕偺妱傝崬傒傪妡偗傞偲偐丄CPU屌桳偺儗僕僗僞傪偨偨偔偲偐丄偦傟偔傜偄偱偟偐巊傢側偄傛偆偱偡丅傕偭偲帪娫傪妡偗偰Verilog傪傗偭偰傎偟偐偭偨側偁丅
丂
仜偦偟偰C尵岅偑巒傑偭偨
丂偄傗乕丄傾僙儞僽儕偲斾傋傞偲埑搢揑偵敾傝堈偔偰偄偄偱偡偹丄C尵岅丅偦偟偰C尵岅偼扴摉嫵姱偑孭楙扴擟偵曄傢偭偨偺偱偡偑丄偙偺愭惗偺嫵偊曽偑旕忢偵忋庤偱敾傝傗偡偄偲偄偆偺傕丄孭楙偺恑捇偑偄偄棟桼偺1偮偩偲巚偄傑偡丅C偲傾僙儞僽儕偱寢峔堘偭偰C偑妝偩側乕偭偰巚偆偺偼儊儌儕偺巊偄曽偱偡偹丅傑偩4擔栚偱億僀儞僞偺愢柧傑偱偼恑傫偱側偔偰攝楍傑偱偟偐傗偭偰偼偄側偄傫偱偡偑丄傾僙儞僽儕偩偲偄傑偄偪敾傝偯傜偐偭偨PUSH-POP偺娭學偑C偩偲戅旔梡曄悢傪攝楍偱梡堄偟偰偍偄偰弌偟擖傟偡傟偽OK偭偰偁偨傝偲偐敾傝堈偄偲巚偄傑偟偨丅傑偨丄曄悢偺慜偵仌傪晅偗偰傾僪儗僗巜掕偟偰擖椡傪曐懚偟丄偦偄偮傪巊偆偲偒偼曄悢柤偱屇傃弌偟偰巊偆偭偰偁偨傝偵偮偄偰偼丄傾僙儞僽儕偩偲僉乕儃乕僪偺IO傾僪儗僗傪儗僕僗僞偵僙僢僩偟乣偭偰姶偠偱30峴埲忋徚旓偟偪傖偆偺偱偡偑丄C偩偲5峴傕偐偐傜偢弌棃偪傖偆偺偑杮摉偵妝丅偨偩C傪怗偭偰偰寢峔擺摼偑偄偐側偄偺偑僼傽僀儖僒僀僘偱偡丅幚嵺偺峴悢偱偼15峴傕側偔僼傽僀儖僒僀僘傕1kb庛偲偄偆僐乕僪偱偁偭偨偲偟偰傕丄僐儞僷僀儔傪捠偟偰幚峴僼傽僀儖偵偡傞偲側偤偐51kb偲偐偵朿傟忋偑偭偰偄傑偟偰丄偙偄偮偩偗偼擺摼偑尵偄傑偣傫丅側傫偱偁傫側偵朿傟傞傫偱偟傚偆偐偹偊丅偦傫側姶偠偱拞妛崅峑帪戙偵偪傚偭偲C怗偭偰偨崰傪巚偄弌偟側偑傜C尵岅偺孭楙傪庴偗偰傑偡丅
仜儎儅僴偲儂儞僟偺嫤嬈
丂儎儅僴偑50cc偺僗僋乕僞乕偺暘栰偱儂儞僟偲嫤嬈偟丄尰嵼儀僩僫儉傗拞崙偱惗嶻偟偰偄傞幵庬傪彨棃揑偵儂儞僟偺孎杮岺応偺儔僀儞偱惢憿偡傞偙偲傪儂儞僟偲柾嶕偟偰偄傞曬摴偑偁傝丄椉幰偐傜傕敪昞偑偁傝傑偟偨丅偙偺審偱嵟弶偼昳幙偺偄偄儎儅僴愝寁偵側傟偽偄偄偺偵偲傕巚偭偨偺偱偡偑丄僶僀僋壆偺偰揦挿偲榖偟偰偄傞偲傗偼傝弌偰偔傞偺偑僽儔儞僪柤偲惗嶻婯柾丅儂儞僟偺惗嶻婯柾偼偐側傝戝偒偔僽儔儞僪僀儊乕僕傕偁傞偺偱儂儞僟偺幵庬儀乕僗偵側傞偺偱偼丄偲偄偆姶偠偱偟偨丅偱丄幚嵺偵徻偟偄拞恎偑弌偰偒偨偺偑曬摴偺梻擔側偺偱偡偑丄傗偼傝儎儅僴偺價乕僲傗僕儑僌傪儂儞僟偺僞僋僩傪儀乕僗偵惢憿偟丄僈儚偲憰旛偩偗偼儎儅僴巇條偵偭偰偙偲偺傛偆偱偡丅傑偨丄堦斒梡偺50cc傛傝偝傜偵僷僀偺彫偝偄攝払梡50cc偺暘栰偱偼GEAR偺攧傟峴偒偑岲挷偱儎儅僴偺傎偆偑僔僃傾傪埇偭偰偄傞傛偆偱偡偑丄偙偪傜偼奐敪偑戝暆偵愭峴偟偰偄傞儎儅僴偺愝寁傪儀乕僗偵椉幮嫤嬈偱奐敪偡傞傛偆偱偡丅傑偁偦偆偟側偄偲僗僋乕僞乕傪嶌偭偰傞3幮嫟搢傟偱偡偐傜偹丅偙偙傊僗僘僉偲僇儚僒僉偑忔偭偐偭偰偔傞偺偐偳偆偐偑偡偛偔妝偟傒偱偡丅 |
| VOL936丗暯惉28擭10寧03擔丗岎捠埨慡偲偐偲偐 |
仜MT偐AT偐偺榑憟偑偁傑傝偵傕攏幁攏幁偟偄審
丂TL偱傑偨MT偐AT偐偺榑憟偑偁傝傑偟偨丅偲偄偭偰傕奜栰偑傗偭偰傞榑憟偵偮偄偰丄椉曽傪僶僇偵偟偰惗抔偐偔尒偰傞偭偰傎偆偑惓夝側傫偱偡偗偳偹丅偙偺庤偺榑憟偑弌偰偔傞偨傃偵攏幁攏幁偟偄側偀偭偰巚偆偺偼丄傑偢MT帄忋庡媊幰偑擇尵栚偵偼AT尷掕柶嫋傪揙掙揑偵尒壓偟偰斀榑偟偯傜偄儌僲偺尵偄曽偱僐僉偍傠偡偭偰偺偼偳偆傛丄偲巚偆偺偱偡丅偦傟偵懳偟偰幚梡揑偐偮巐椫巗応揑偵AT偱廩暘偲懽慠帺庒偲AT攈傕峔偊偰偄傟偽偄偄儌僲偺丄MT偺憖嶌偼TVT偵偼傞偐偵楎傞偲偐丄嵟怴揹巕僨僶僀僗傕娷傔偰斲掕偱偒側偄MT攈偼拞搑敿抂偲偐丄儗儀儖偺掅偄慀傝斀榑傪偟偰偟傑偆偺偱丄偍屳偄壩偵桘偱偝傜偵岥榑偑壛懍偡傞傢偗偱偡傛丅摿偵傕偭偲傕攏幁攏幁偟偄斀榑偑乽MT怣幰偺傾儂傜偟偝偭偰AT尷掕傪乽嵟掅尷偺憖嶌傕偱偒側偄傾儂乿偭偰尵偆妱偵偼戝敿偼尰戙揑側幵偵忔偭偰傞偲偙偩傛偹丅偠傖偁偍慜僷儚僗僥傕僄傾僐儞傕TCS傕ABS傕側偄幵傪塣揮偟偰傒傠傛丄偲丅乿偲偄偆搝丅偙偆偄偆尵偄曽傪偟偰偟傑偆偲AT攈偭偰傗偭傁傝楎摍姶偺夠側傫偩側乕偭偰尒傜傟偪傖偆傢偗偱偡丅
丂偪側傒偵巹偺僗僞儞僗偼乽忔傝偨偄搝偵忔偭偲偗傛乿偱偡偑丄柶嫋偵偮偄偰偼乽帪娫偲旓梡偑嫋偡側傜嬌椡儅僯儏傾儖幵偺嫵堢傪庴偗偰偍偒側偝偄乿偱偡丅崱偳偒AT偽偭偐傝偱柍懯偩偭偰巚偆偐傕偱偡偑丄帺摦壔偝傟偨憰抲傪帺暘偱憖嶌偡傞偵偁偨偭偰偦偺憰抲偺摦嶌尨棟傗堄枴傪棟夝偡傞偵偼庤摦偺憰抲傪巊偆傎偆偑棟夝偑懍偄傫偱偡偑丄偙傟帺摦幵偺塣揮傕摨偠側偺偱偡丅側偤敪恑弌棃傞偺偐丄僊傾偼側偤偁傞偺偐丄偲偄偆堄枴偑尒偊偰偒傑偡丅偦傟傪棟夝偟偰塣揮偡傞偲幵偺塣揮偭偰怓乆曄傢偭偰偒傑偡偟丄AT幵偵偁傝偑偪側僟儔僟儔掅懍偱憱傞偗偳廃傝偑尒偊偰側偄枱慠塣揮傕偐側傝杊偘傑偡丅偱偡偺偱丄弌棃傟偽MT庢偭偲偗丄婡夛偑偁傟偽堦搙偼MT幵強桳偟偲偗丄弌棃傟偽偺斖埻偱丄偲偄偆僗僞儞僗偵側傝傑偡丅巹帺恎偼MT偲AT傪峴偭偨傝棃偨傝偟偰傑偡偑丄崱夞MT偺寉僩儔傪強桳偡傞傛偆偵側偭偰丄岎嵎揰偱偺掆巭傗嵞敪恑丄塃嵍愜偱偺妋擣偼埲慜偵憹偟偰廫擇暘偵偡傞傛偆偵側傝傑偟偨偟丄妱傝崬傑傟偨傝偟偰傕乽傑偁偊偊偐乿偱嵪傑偣偰偟傑偆傛偆偵側傝傑偟偨丅AT偩偗惗妶傛傝MT傕崿偞偭偰傞傎偆偑奿抜偵埨慡堄幆偑崅傑偭偰偄傑偡丅偁偲丄傛偔尵傢傟傞廰懾傗嶁摴側偺偱偡偑丄姷傟偰偟傑偆偲屇媧偟偰傞偺偲摨偠偱壗傕峫偊偢偵僼僣乕偵憖嶌偟偰偄傑偡偺偱丄側傫傜栤戣偼側偄偱偡偟晄曋偝傕姶偠傑偣傫丅寉僩儔偱僋儔僢僠偑寉偄偲偄偆偺傕偁傝傑偡偑丄傑偁偙傫側傕傫偱偡丅
丂
仜MT偺拞偺榖
丂幚偼抪偢偐偟側偑傜僲儞僔僋儘儈僢僔儑儞偺峔憿偼戝懱棟夝偟偰偄偨偺偱偡偑丄尰戙庡棳偺忢帪姎傒崌偄幃偺僔儞僋儘晅儈僢僔儑儞偑偳偆偄偆尨棟偱摦嶌偟偰偄傞偺偐丄嵟嬤傑偱傛偔抦傝傑偣傫偱偟偨丅尰戙偺儅僯儏傾儖僩儔儞僗儈僢僔儑儞偼慜恑僊傾偼偡傋偰姎傒崌偭偨忬懺偱慻傒棫偰傜傟偰偄傑偡丅儕僶乕僗僊傾偩偗偼撈棫偟偰偄傑偡丅傑偨丄慜恑僊傾偵偼僔儞僋儘儊僢僔儏婡峔偭偰偺偑晅偄偰偄傑偡丅傑偢曄懍偺尨棟偱偡偑丄奺僊傾偼僇僂儞僞乕僔儍僼僩偲傾僂僩僾僢僩僔儍僼僩偵拡傇傜傝傫忬懺偱巋偝偭偰偄傑偡丅曄懍儗僶乕傪憖嶌偡傞偲僗儕乕僽偲偄偆娐偑儗僶乕偵傛傝摦偐偝傟丄栚揑偺僊傾偲僔儍僼僩傪僗僾儔僀儞偱偐傒崌傢偣傞偙偲偱弌椡偑揱払偝傟傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅偱丄僔儞僋儘婡峔偼偳偆偄偆儌僲偐偲偄偆偲丄偦偺僗儕乕僽偲僊傾偺娫偵傕偆1偮儕儞僌傪憓擖偟丄僔儍僼僩偲僊傾偺夞揮懍搙偑崌傢側偄偺傪忋庤偔崌偆傛偆偵挷惍偝偣傞婡峔偱偡丅youtube偵摦夋偑偁傞偺偱偦傟傪尒傞偲摦嶌尨棟偑暘偐傝傗偡偄傫偱偡偑丄傑偁偁傫側扨弮側曽朄偱忋庤偔夝寛偟偰傞側乣偭偰偺偑杮壒偱偡丅偟偐偟偙偆偄偆偺傪摦夋偱尒偰愢柧偝傟傞偲暘偐傝傗偡偄偱偡偟丄壗偐僩儔僽偭偨偲偒偵媈偆応強傕峫偊傗偡偔偰偄偄偱偡偹丅
丂
仜墶抐曕摴偲曕峴幰曐岇
丂嵟嬤僱僢僩偱偪傚偭偲弌偰偄偨乽墶抐曕摴偱懸偭偰傞曕峴幰偑偄傞偲偒偵掆巭偟側偄幵偼9妱乿偲偄偆JAF偺挷嵏寢壥偑偁傝傑偟偨偑丄巹偼偙偺審偵娭偟偰偼乽婎杮揑偵巭傑傞乿偱夞摎偟偨1妱懁偵偄傑偡丅偱丄嵟嬤傗偭偲偙偝寈嶡偐傜乽杮恖曔傑偊偰婲慽偟偨偐傜欔偄偰偄偄傛乿偲尵傢傟偨帠屘偑偁傝傑偟偰丅攑僛僢僩偝傫偱憱峴拞偵偲偁傞墶抐曕摴偱榁攌偵摴傪忳偭偨偺偱偡偑丄巹偑40噏偐傜尭懍偟偰掆巭悺慜偵屻傠偵偮偄偰偄偨僴僀僄乕僗偑壛懍偟側偑傜捛偄墇偟傪妡偗丄栚偺慜偱榁攌傪挼偹旘偽偟偰摝憱偟傑偟偨丅偆傢偍丄鐎偒摝偘偩傛偍偄偍偄偭偰摉慠偦偺応偱掆幵偟偰110斣偲119斣傪庤攝偟偨傫偱偡偑丄摓拝偟偨寈嶡姱偑乽偁乕偦偺SD僇乕僪丄採嫙偟偰偹乿偱慜屻僇儊儔偺MicroSD2枃儃僢僔儏乕僩丅偦偺SD偺塮憸偑寛傔庤偵側偭偰僗僺乕僪戇曔偲婲慽偵宷偑傝傑偟偨丅傑偁丄偦傫側姶偠偱曕峴幰曐岇偑偦傕偦傕媊柋偱偁傞偙偲傪朰傟偰傞攏幁偑偁傑傝偵傕懡偄傢偗偱偡傛丅僴僀僄乕僗偺攏幁濰偔丄慜偺寉僩儔偑楬挀偟偨偐傜捛偄敳偄偨偺偵壗偑埆偄偲嫃捈偭偰傞傛偆偱丄傑偁嵸敾偑妝偟傒側傢偗偱偡偑丅偙偺審偱寈嶡姱傕尵偭偰偨偺偱偡偑杮摉偵墶抐曕摴偱偺曕峴幰曐岇傪偍偞側傝偵偟偰傞恖偑懡偡偓傞偦偆偱偡丅偨偩巹偼偙偺審偵娭偟偰偼寈嶡姱偵偼偭偒傝偲乽偦傕偦傕曔傑偊傞堄枴偺敄偄懍搙堘斀偽偭偐傝曔傑偊偰丄杮棃傕偭偲婋尟側帺揮幵偺晄朄塣揮傗幵鏿慡斒偺堦帪掆巭丒愒怣崋柍帇傪慡慠庢傝掲傑傜側偄偐傜巗柉偵僫儊傜傟偰傞傫偠傖側偄偱偡偐乿偲尵偄曻偭偨傫偱偡偑偹丅側偍偙偺拞偱夵傔偰寈嶡姱偵妋擣偟偨帠埬偵乽偠傖偁帺揮幵偼偳偆偄偆埖偄丠乿偭偰偺偑偁偭偨傫偱偡偑丄寈嶡姱濰偔乽帺揮幵偼幵鏿側偺偱曐岇偟側偔偰偄偄偟桪愭揑偵搉傜偣傞昁梫偼側偄丅巕嫙偺帺揮幵偱偁偭偰傕幵鏿偼幵鏿側偺偱桪愭尃偺偁傞傎偆偑桪愭尃偵廬偭偰埨慡傪妋擣偟側偑傜捠峴偡傟偽栤戣側偄乿偲偄偆偙偲偱偟偨丅偲傝偁偊偢傾儗偱偡丄怣崋偺側偄墶抐曕摴偺応崌丄偪傖傫偲曕峴幰曐岇偟傑偟傚偆丅 |
| VOL935丗暯惉28擭09寧26擔丗偪傖傫偲梊廗偟偰偔傟傛 |
仜ENKEI偺傾儖儈儂僀乕儖曗廋偺偝傜偵懕偒
丂偊乕偲丄偲傝偁偊偢堦扷敀偔揾偭偨傫偱偡偑丄僒僼偱偳偆傕朅偵偟偪傖偭偨偲偙傠偑偁偭偨傒偨偄偱丄偦傟偵婥偯偐偢揾偭偰偟傑偭偰巇忋偘揾憰偟捈偟寛掕偱偡丅崱夞偼掕斣偺僀僒儉偺僄傾乕僂儗僞儞傪巊偭偰偄傞偺偱偡偑丄崱夞捝愗偵姶偠偨偺偑丄偲偵偐偔娛僗僾儗乕偩偲傾乕儉宍忬偑嵶偐偄儂僀乕儖偩偲惉宆偑嵶偐偄応強偵儈僗僩偑慡慠擖傜側偄偙偲偱偡丅偙傟偑僐儞僾儗僢僒乕偵宷偖揾憰梡僈儞偩偲僕僃僢僩偺峀偑傝傪曗懌偟偨傝峀偔偟偨傝偱偒傞偺偱偐側傝挷惍偑岠偔傫偱偡偑丄側傫偣娛僗僾儗乕偱弌棃傞偺偼娛傪壏傔偰埑椡傪偁偘傞偙偲偔傜偄丅埑偼崅偔弌椡偼嵶偔丄偲偐挷惍弌棃側偄偺偑偪傚偭偲恏偄偱偡丅崱夞丄僂儗僞儞揾憰傪偟偰偄偰巚偭偨偺偼丄杮棃敪怓偺椙偄儔僢僇乕偵斾傋偰偐側傝敪怓偑椙偄偙偲偱偡丅幚偼敪怓偦偺傕偺偼僂儗僞儞傛傝儔僢僇乕偺曽偑偄偄傫偱偡傛丅偱傕側偤僂儗僞儞偺傎偆偑鉟楉偵怓偑弌傞偺偐偲偄偆偲丄梟攠偑婗敪偟偰宍惉偝傟傞揾枌偺岤偝偑5攞偔傜偄暘岤偄偐傜偱偡丅暘岤偄暘宍惉偝傟偨旐枌偼壓抧偺墯撌傪廍偄傑偣傫偟丄忋庤偔姡憞懍搙傪挷惍偱偒傟偽儈僗僩偱棻忬偵晅拝偟偨揾椏偑傋偨乕偭偲峀偑偭偰枌宍惉偡傞帪娫揑梋桾傕偁傝傑偡丅崱夞巊偭偰傞僂儗僞儞僗僾儗乕偼10暘偱揾枌宍惉偝傟傑偡偑丄僜僼僩99傗儂儖僣偺儔僢僇乕偼懍姡惈偱偡偺偱丄儈僗僩偑揾枌偵側傞慜偵屌傑偭偰傞偺偱儅僢僩揾憰偭傐偔側傝傗偡偄偲傕峫偊傜傟傞傫偱偡丅偲傝偁偊偢幐攕偟偰嶍偭偨偲偙傠埲奜偼偐側傝枮懌偺崅偄巇忋偑傝偱偡偟丄傕偆1杮捛壛偱峸擖偟偰傞偺偱偝傜偵忋揾傝偟偰偐傜僂儗僞儞僋儕傾偱巇忋偘偨偄偲巚偄傑偡丅偟偐偟乧乧僞僀儎傪擖傟傜傟傞偺偼偢偄傇傫愭偵側傝偦偆偩側偁乮丩丒冎丒丮乯
丂
仜崱僔乕僘儞偺傾僯儊偑偄偔偮偐廔傢偭偨
丂偲傝偁偊偢懩惈偱尒偰偄偨傕偺偲偐怓乆偁偭偨偺偱偡偑丄崱婫偢偽敳偗偰柺敀偐偭偨1偮偑乽偙偺旤弍晹偵偼栤戣偑偁傞両乿偱偟偨丅偙傟丄僱僞偝偊偁傟偽4僋乕儖峴偗偦偆側傾僯儊偱偡偹丅尨嶌偼撉傫偱側偄偺偱偡偑傾僯儊偼偪傖傫偲媟杮偑楙傟偰偄偰丄榖偵偪傖傫偲僆僠偑晅偔傛偆偵側偭偰偄偨傝偄偄榖偱廔傢傞傛偆偵側偭偰偄偰丄偝傜偵嶌夋偑挌擩丅偟偐傕傒偢偒偪傖傫偺嶌夋偑偄偐偵傕拞妛惗偭傐偄姶偠偱傕偆壜垽傜偟偔偰偱偡偹丅偤傂偤傂戞2婜傪婜懸偟偨偄傾僯儊偱偡丅NEW GAME傕尨嶌傪拤幚偵偒偭偪傝傾僯儊壔偟偰偒偰丄僔僫儕僆揑攋抅傕側偔奊暱傕偢偭偲埨掕偟偰偄偰杮摉偵弌棃偺椙偄傾僯儊偱偟偨丅偙傟傕偦偺偆偪戞2婜傗傞傫偠傖側偄偐側偁丅堦曽偱巆擮偩偭偨側乕偭偰巚偆傾僯儊偺1偮偑儅僋儘僗僨儖僞偱偟偨丅儅僋儘僗僔儕乕僘偺拞偱傕寢峔昡壙偑掅偄嶌昳偵側傞傫偠傖側偄偱偟傚偆偐丅偁偲丄榖偼偐側傝攏幁偱扨弮偵壗傕峫偊偢偵尒偰偄傜傟偨偩偗偺傾僯儊偼僋僆儕僨傿傾僐乕僪丅搑拞偱戝懱偺僆僠偼撉傔偨偗偳嵟屻偺嵟屻偱忋庤偔梊憐傪棤愗傜傟偨姶偠偱偟偨丅偨偩偟偁偺嶌夋偼偹偉傛乧乧丅慡曇捠偠偰僋僜嶌夋偲挻僋僜嶌夋偑擖傝崿偠傞崜偄弌棃偱偟偨丅偁偲丄Re僛儘傕2僋乕儖偱廔傢傞偺偑寢峔巆擮側姶偠偱偟偨偑丄斀柺丄Web楢嵹斉偺捠傝偵恑傓偺偩偲偟偨傜偡偱偵儗儉偼乽怘傢傟偨乿屻側偺偱丄偙偺愭偺揥奐偑僽儖乕側偩偗偵偭偰偲偙傠偱偡丅偪側傒偵搑拞偱幪偰偨傾僯儊偺拞偵傾僋僥傿僽儗僀僪2婜偑偁傝傑偡丅幒挿栚摉偰偱尒偰偼偄偨傕偺偺丄2婜偼僔僫儕僆偑傾儗僎偡偓偰偪傚偭偲尒偰偄傜傟側偔側傝傑偟偨丅偲傑偁偙傫側姶偠偱偡偑丄棃婜偺傾僯儊偼壗偵婜懸偡傟偽偄偄偺傗傜丅
丂
仜孭楙峑偺傾僙儞僽儔偺懕偒
丂僨僶僢僌儌乕僪偱偺PC忋偺傒偱偺幚峴偐傜幚嵺偵儃乕僪傪摦偐偡孭楙偵堏峴偟偰偄傑偡偑丄僫僯僎偵偙偺孭楙偑偨偭偨偺2廡娫偟偐側偄忋偵丄廡弶傔偺戜晽偱媥島偑敪惗偟偰偝傜偵抶墑婥枴偵側偭偰偰僋僜儚儘偱偡丅偟偐傕憡曄傢傜偢側偺偱偡偑丄嫵姱偑帠慜偵僥僉僗僩傪撉傓偙偲傕偣偢島媊偵椪傫偱偍傝丄島媊偺拞偱弶傔偰嫵杮傪撉傒側偑傜媈媊傪彞偊偰峫偊巒傔偨傝丄帺暘偑傗傝偨偄偙偲傪巚偄偮偒偱偦偺応偱傗偭偪傖偆偺偱榖偑廲墶偵旘傫偱偟傑偭偰傕偆側偵偑側偵傗傜丅島媊寁夋偵傑偭偨偔寁夋惈偑側偔峴偒摉偨傝偽偭偨傝側偺偱杮摉偵崲傝傑偡丅傑偨丄傕偭偲崲傞偙偲偑丄嫵杮偺拞偺壽戣偲夞摎椺偲偟偰椺帵偝傟傞僗僋儕僾僩偺拞恎偑慡偔暿暔偩偲偐丄偦傕偦傕愝栤偲夞摎偑慡偔暿偲偄偆偺偑懡乆偁傞偙偲偱偡丅愭弎偺墶摴偑懡偄審傕偁偭偰島媊帪娫偑傂偭敆偟傑偔偭偰傞偺偱摉慠椺戣偺夝愢側傫偰傑偭偨偔偁傝傑偣傫丅偍偐偘偱慡慠棟夝搙偑怺傑傜側偄偺偑暊棫偨偟偄偲偄偆偐側傫偲偄偆偐丅偲傝偁偊偢偁傞掱搙嫃巆傝傗憗弌偱帺暘偨偪偱偁傞掱搙婃挘偭偰偼傒偰偄傞偺偱偡偑丄偄傗傎傫偲崲傝壥偰偰偄傑偡丅 |
| VOL934丗暯惉28擭09寧19擔丗怘傢偢寵偄偼椙偔側偐偭偨 |
仜傾儖儈儂僀乕儖偦偺屻
丂徻嵶偼youtube偲僯僐摦偵敋寕偡傞梊掕仌HTML偵傑偲傔傞梊掕偱偡偑丄偲傝偁偊偢偁傑傝偵傕儁儞僉偺晅拝偑崜偐偭偨1杮偼儕儁僀儞僩偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅僱僢僩偱尒偰偰傕儂儉僙儞偱1500墌偔傜偄偱攧傜傟偰偄傞僂儗僞儞僗僾儗乕偱揾傝側偍偟偰傞椺偑寢峔懡偔丄傑偨傒側偝傫堄奜偲鉟楉偵揾傜傟偰偄傑偡丅傛偆偼偳偙傑偱壓抧傪挌擩偵嶌傞偐偑彑晧側偺偼儃僨傿偺嵞揾憰偲摨偠偱偡偹丅偱丄尰忬偱偡偑丄晅拝偟偨儁儞僉偵偮偄偰偼慡晹棊偲偟傑偟偨丅240斣偺儁乕僷乕偱悈尋偓偟偰鉟楉偝偭傁傝嶍傝棊偲偟偰傗傝傑偟偨丅傑偨丄偮偄偱偵僆儌僥柺偺儕儉側偳偵偮偄偰傞僈儕彎傕弌偭挘偭偰傞晹暘偼暯傗偡傝偱嶍傝丄墯傫偩晹暘偵偼慡晹僷僥傪楙傝崬傒丄嬻尋偓偱尋偓弌偟偟偰鉟楉偵偟傑偟偨丅慡懱揑偵240斣偱嶍偭偰傞偺偱懌晅傕偍傢偭偰傑偡偐傜丄偁偲偼揤岓偑夞暅偟偨傜僔儕僐儞僆僼亜僾儔僒僼亜僷僥偺庤捈偟亜僾儔僒僼亜悈尋偓亜杮揾憰偱偡偹丅傑偁側傞傛偆偵側傞偱偟傚偆丅儕儁僀儞僩傪棅傓偲晛捠偵1杮2枩庛偟傑偡偟偹丅
丂
仜NEX-3C
丂偔傑偔傑傫偠傖側偄撧椙偺僇儊僋儔側桭恖偐傜搉偝傟傑偟偨丅乽偲傝偁偊偢怘傢偢寵偄偟偰傫偲栙偭偰巊偭偰傒傠乿偲偄偆偙偲偩偦偆偱丄棊壓昳側僕儍儞僋傪嵞惗偟偨敿僕儍儞僋傪柍婜尷儗儞僞儖偡傞偙偲偵丅偨偩晅偄偰偒偨拞偵1杮傕E儅僂儞僩儗儞僘偑側偔丄E-SR丄E-Y/C丄E-M偺3偮偺曄姺傾僟僾僞乕偲儎僔僇偺28噊F2.8丄50噊F1.9偲偄偆僴僫偐傜徖恖尷掕偺憰旛偱傗偭偰偒偰偰憪惗傗偡偟偐偁傝傑偣傫丅巊偄曽偼傎偲傫偳幚偼暦偄偰側偐偭偨偺偱偡偑偲傝偁偊偢僥僉僩乕偵悢枃傁偟傖傁偟傖丅偆乕傫丄傗偭傁儅僂儞僩僟僾僞乕偱柍棟傗傝巊偭偰傞偺偱業弌偑寢峔傾儗偱偡丅僸僗僩僌儔儉傪尒側偑傜忋庤偔業弌曗惓傪偟偰僑僯儑僑僯儑偱偡偹丅堦曽偱惁偔曋棙側偺偑MF傾僔僗僞儞僩丅僺儞僩偑崌偭偰傞晹暘偑愒偔曄壔偡傞偲偄偆搝側傫偱偡偑丄偙傟偑偁傞偍偐偘偱寢峔偒偭偪傝僺儞偑捛偄崬傔傑偡丅夋幙偵娭偟偰偼傑乕偦傟側傝偭偰偲偙傠偱偡偹丅傕偆1偮柺敀偐偭偨偺偼丄嬧墫偩偲杴梖偺儗儞僘偲尵傢傟偨傝丄攚宨偑擇慄儃働偟偰奐曻偱偼巊偄偯傜偄偲尵傢傟偰偄偨儗儞僘偱偡偑丄NEX-3C偵宷偖偲偦偆偄偆峳傟傞儃働偺孹岦偑徚偊偰鉟楉偵嶣傟偨傝偟傑偡丅堦曽偱尦乆僐儅廂嵎偑庒姳嬧墫偱傕尒偊偰偨儗儞僘偺応崌丄業崪偵僷乕僾儖僼儕儞僕偑弌偨傝丄僐儅廂嵎偑弌偨傝偟偰丄偙傟偱儗儞僘偺枴傪偳偆偙偆尵偆偺偼婋尟偩側乕偭偰姶憐偱偟偨丅
仜嵍傂偞偺懕偒
丂嵍傂偞偱偡偑丄偁偺偁偲MRI傪嶣傝偵偄偭偰怓乆専嵏偟偨偺偱偡偑丄寢榑偐傜尵偆偲敿寧斅偺梀棧暔偭偰傕偺帺懱偑懚嵼偟傑偣傫偱偟偨丅偔偦乕丄偦傟傪尵偄弌偟偨偁偺傗傇堛幰傔乧乧丅旼奧崪偵偮偄偨偲偘偺廃傝偺墛徢偑寖偟偔偰旼慡懱偵媦傫偱偄偰旼偺忋偺曽偵悈偑偨傑偭偰偄傞偺偑捝偝偺尨場偠傖偹丠傒偨偄側姶偠偱偟偨丅偄偭傐偆偱敿寧斅偼偪傚偭偲儅僘偄忬懺偵側偭偰偄傑偟偨丅摿偵撪懁偑側傫偐埑椡偱怢傃偰曄宍偟偰偄偨偺偱偡偑丄偙傟幚偼帺揮幵慖庤帪戙偐傜傛偔捝傓応強偱丄偦偺偙傠偐傜敿寧斅偼懝彎偼偟偰側偔偰傕曄宍偟偰偄偨偲偄偆偙偲偱偡丅崱屻丄敿寧斅偑尨場偱曕峴偵晄嬶崌偑弌傞偺偼娫堘偄偑側偄偲偺偙偲偱丄偐側傜偢懱廳偼棊偲偡傛偆偵偭偰尵傢傟偨偺偱偦傠偦傠寵乆側偑傜塣摦傪嵞奐偟側偗傟偽偲巚偭偰偄傑偡丅
丂
仜暯摍偭偰側傫偩傠偆偹
丂twitter偱嵟嬤偪傜傎傜抝彈暯摍偺榖偑夞偭偰偒傑偡丅TL忋偵偼嬌抂側僼僃儈僯儞丒僕僃儞僟乕庡媊偺彈惈傕偪傜傎傜崿偞偭偰偄傞偺偱偦偺恖偨偪偺嬌抂側敪尵傗RT偐傜榖偑敪揥偡傞偙偲偑庡側傫偱偡偑丄嵟嬤僇僼僃傾儖僼傽宯偺僼僅儘儚乕偲儊儞僔儑儞偱夛榖偟偰偄偰丄搝傜偺攚宨偲偐偦偺曈傪側傫偲側偔棟夝偟偨姶偠偱偡丅偁偺彈惈帄忋庡媊幰側曽乆偼寢嬊偺偲偙傠丄80乣90擭戙偵弾柋側偳偺OL偱偡傜擭娫徿梌偑100枩弌偰偨傛偆側帪戙偺姶妎偵婎偯偄偰敪尵偟偰偄傞傛偆側姶偠偱丄壠偵偲傜傢傟傞傛傝岲偒側偙偲傗偭偰僆僇僱栣偆傎偆偑偄偄偠傖側偄揑側偲偙傠偑偁傞傫偩傠偆偭偰偄偆姶偠偱偡丅偦偙偵帺屓幚尰偲廳偹崌傢偣偰怓乆尵偭偪傖偭偰傞丄偲丅偲偙傠偑嶐崱偺10戙乣20夁偓偺彈偺巕偨偪偼傕偭偲抧偵懌偺拝偄偨敪尵傪偟偰偄偰丄抝彈偺栶妱暘扴傪偒偭偪傝偡傞側傜扷撨偑奜壿壱偄偱巹偼壠傪愗傝惙傝偡傞偭偰巕偑懡偔丄僼僃儈僯儞側傾儔僼僅乕丒傾儔僼傿僼偨偪偼偦傟傕婥偵怘傢側偄傒偨偄偱偡偹丅偱傕巹偲偐傕巚偆偺偱偡偑丄抝彈偺惈嵎偑偁偭偰弌棃傞偙偲偵堘偄偑偁傞傫偩偐傜壠掚塣塩偱栶妱暘扴傕昁梫側傫偱偡傛丅抝彈偳偪傜傕抝偺栶妱偱偼椉椫偑惉傝棫偨側偄傫偱偡傛丅嵶偐偄壠帠偺暘扴偲偐偼偦傝傖乕晇晈偱怓乆寛傔傟偽偄偄傫偱偡偑丄偦偙傪偡偭旘偽偟偰乽壌偼奜偱摥偄偰傞偐傜壠偼擟偣偨乿偱娵搳偘偡傞抝偼懯栚丄偱傕偪傖傫偲暘扴偱偒傞側傜偦傟埲奜偼抝彈偺惈嵎偼偁偭偰偟偐傞傋偒偩偲巚偭偰偄傑偡丅偱傕偙傟偑僼僃儈僯儞偨偪偵偼捠偠側偄偺偑側傫偩偐側偀丄側傫偱偡傛丅
丂
丂偁偲丄偙傟傕嵟嬤巚偆偙偲偱偡偑丄偦偺僼僃儈僯儞偨偪偑擇尵栚偵彮巕崅楊壔懳嶔偲偟偰丄婛崶壠掚傊偺巕堢偰巟墖傪廩幚偝偣傠偲偟偐尵傢側偄偲偙傠偑峫偊堘偄偟偰傞傫偠傖側偄偐偲巚偭偰偄傑偡丅巹偺悽戙偺枹崶棪偭偰嫲傠偟偔崅偔側偭偰偄傑偡丅枹崶棪偑忋偑傞偲偦傟偩偗巕嫙偑弌棃傞僇僢僾儖偑尭傞偭偰偙偲側偺偱摉慠彮巕壔偑恑傓傢偗偱偡丅巹傜儌僥側偄抝惈偐傜偟偰寢崶偳偙傠偐斵彈偡傜弌棃側偄偲偙傠偼怓乆偁傞傫偱偡偑丄1偮偼乽偦傕偦傕帺暘偺幮夛揑恎暘傪揤攭偵妡偗偰傑偱彈惈偵傾僞僢僋偡傞儊儕僢僩偑側偄乿揰偱偡丅彈惈懁偑抝惈傪慖傇億僀儞僩偭偰寢峔尩偟偄栚慄偱慖傫偱傞傛偆偱偡偑丄愭弎偺僼僃儈僯儞偳傕偺惡偺僨僇偝傕偁偭偰丄嵟嬤偼婥偵怘傢側偄傾僞僢僋傪偟偰偒偨抝惈傪僂僜偱埆昡傪嶶乆忺傝晅偗偰偐傜SNS偱抐嵾偟偰幮夛揑偵枙嶦偡傞丄側傫偰椺傪偪傜傎傜尒偰偄傑偡丅抝惈偐傜偟偨傜崱偺惗妶偱傕惛堦攖側偺偵偦傫側抧棆傪摜傓婋尟惈傪朻偡偔傜偄側傜抝彈岎嵺偡傜昁梫側偄丄偲偄偆傢偗偱偡丅晅偒崌偄偑側偄側傜偦傝傖乕楒垽寢崶帄忋庡媊偺尰戙偩偲枹崶棪忋偑傝傑偡傛丅彈惈偼彈惈偱宱嵪椡丄尒偨栚丄帺暘傊偺娒傗偐偣偭傉傝側偳偱揤攭傪妡偗偰偄傑偡偟丅惓捈丄婛崶壠掚偺働傾傪嫨傫偱偄傞偲偦傝傖妝偱偡丅偩偭偰婛偵惗傓忬懺偵側偭偰傞傢偗偱偡偐傜丅偱傕杮摉偵彮巕壔傪懳嶔偡傞偭偰偄偆側傜丄傑偩寢崶偟偰側偄搝傜傪寢崶偵岦偐傢偣傞搘椡傪偡傞曽偺傕戝帠偠傖側偄偺丄偲巚偆傢偗偱偡傛 |
| VOL933丗暯惉28擭09寧12擔丗旼偑捝偄 |
仜傑偨旼偑捝偔側偭偨
丂妛惗帪戙偐傜偢偭偲嵍傂偞偑挷巕埆偄傫偱偡偑丄崱夞偼妛惗帪戙偐傜偺挷巕埆偝偺億僀儞僩偐傜暿審偑墛徢傪婲偙偟偰偝傜偵埆壔偝偣偨偲偄偆僷僞乕儞偱偟偨丅妛惗帪戙偭偰偐MTB偱梀傃巒傔偰偟偽傜偔偟偰丄儁僟儕儞僌偺埆偝側偳偐傜嵍傂偞偺敿寧斅傪彮偟攳棧偝偣偰偟傑偭偨傛偆偱丄2噊庛偔傜偄偺戝偒偝偺敿寧斅偺偐偗傜偑旼偺拞傪偖傞偖傞摦偄偰傞偺偼MRI娤嶡側偳偱埲慜偐傜暘偐偭偰偄傑偟偨丅偙偄偮偑応崌偵傛偭偰偼旼娭愡偵埆偝傪偟偰捝傒偵側偭偰偄傞傫偱偡偑丄崱夞偼偦傟偺墛徢偐傜偝傜偵丄旼奧崪偵惗偊偨僇儖僔僂儉偺僩僎偺廃埻偺慻怐偑墛徢傪婲偙偟丄捝偝傪壛懍偟偰偄傞偭偰偙偲偱偟偨丅偙偺僇儖僔僂儉偺僩僎丄晛抜偩偲纟偵偟偐偱偒側偄傫偱偡偑丄偳偆傕崱夞偼旼奧崪偵弌棃偨偲偄偆偐丄悘暘慜偐傜懚嵼偟偰偰憡摉嫄戝壔偟偰偄傞傛偆偱偡丅摉柺丄偙偄偮偲忋庤偔愜傝崌偭偰偄偐偹偽側傫偱偡偑丄偝偰偼偰丅偪側傒偵崱夞偼敿寧斅偺偐偗傜偑偳偆側偭偰傞偐偺挷嵏傕偁傞偺偱旼偺MRI傪10悢擭傇傝偵嶣塭偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅
丂
仜嶃恄僼傽儞偑婎杮揑偵嫄恖僼傽儞偑巰偸傎偳寵偄側棟桼
丂25擭傇傝偺桪彑偩偭偨偲偄偆偙偲偱丄嶃恄偑懯栚偩偲暘偐偭偨搑抂偵崱擭偼僇乕僾墳墖偵偝偭偝偲愗傝懼偊偰偨巹偲偟偰傕寢峔婌偽偟偄尷傝偱偡丅偝偰丄偙偺審偱幚偼寢峔僱僢僩偱怓乆傾儗僎側榖傪暦偄偰偄傑偡丅偲偄偆偐傾儗僎側懳徾偑儌儘偵僕儍僀岞偙偲僕儍僀傾儞僣僼傽儞側傫偱偡偑偹丅峀搰偵儅僕僢僋偑揰摂偟偰偁偲1働僞偭偰姶偠偵側偭偨偙傠丄僼僅儘儚乕偺峀搰僼傽儞偵懳偟偰僕儍僀岞偑幪偰戜帉偺傛偆偵丄乽CS傪彑偪敳偗傞曐徹傕側偄偟丄傛偟傫偽擔杮僔儕乕僘偵弌偨偲偟偰傕岎棳愴偺寢壥偐傜僗僩儗乕僩晧偗偟偰廔傢傝偩傠偆乿傒偨偄側尵梩傪梺傃偣傜傟偨偦偆偱偡丅偄傗乕丄巹偺拞偺僕儍僀岞偭偰戝懱偙偆偄偆僀儊乕僕側傫偱偡傛丅偲偄偆偺傕丄巕嫙偺偙傠偐傜惗悎娭惣宯偺廧恖or娭惣3戙栚偔傜偄偺廧恖側巕嫙偼戝掞僩儔僉僠側傫偱偡偑丄恊偑抧曽弌恎偺廤抍廇怑幰傒偨偄側壠掚偼屼懡暘偵楻傟偢僕儍僀岞偱偟偨丅偦偟偰摉帪偺嶃恄偼徍榓61擭偙偦桪彑偟偨傕偺偺偛懚偠偺偲偍傝惁偔庛偐偭偨偺偱偡丅傫偱丄僕儍僀岞偳傕偑擇尵栚偵偼乽偦傫側庛偡偓偰彑偰傕偟側偄媴抍傪墳墖偟偰偰壗偑柺敀偄偺偐丅彑偪傕偟側偄晧偗將媴抍傪傾儂僤儔壓偘偰柍懯偵墳墖偟偰傞偐傜偍慜傜廔傢偭偰傞傫偩乿傒偨偄側朶尵傪寢峔掕婜揑偵揻偐傟傞傢偗偱偡傛丅偙傟偑巕嫙摨巑偺岥榑偩偭偨傜傑偩壜垽傜偟偄偺偱偡偑丄戝恖摨巑偱傕戝懱偙偆偄偆岥榑偺偒偭偐偗傪嶌傞偺偑僕儍僀岞偱傗傝岥偑偦傟丄僩儔僉僠偼偲偄偆偲偦傟偵乽嬥偵儌僲尵傢偣偰慖庤攦傢傫偐偭偨傜恖堳懙偊傕弌棃傫偔偣偵乿偲側傞傢偗偱偡偑丄摉慠岦偙偆偼晧偗惿偟傒偩偲丅傫偱墸傝崌偄偵側傞傢偗偱偡偹乕丅偙偆偄偆宱尡傪嶃恄僼傽儞偼愴屻偢偭偲孞傝曉偟偰偒偰傞偺偱嫄恖僼傽儞偲偄偆懚嵼偑寵偄側傢偗偱偡傛丅
丂
仜寉僩儔偺傾儖儈傪庤偵擖傟偨
丂攑僛僢僩偝傫偺壞僞僀儎梡偵偢偭偲傾儖儈傪扵偟偰偄傑偟偨丅13僀儞僠偺5.0J丄僆僼僙僢僩偑亄40乣50偔傜偄偭偰偺偱偡丅傑偨擖傟傞僞僀儎偵偮偄偰傕怓乆挷嵏傪偟偰偄偨偺偱偡偑丄堦斣懍搙寁偺岆嵎偑彮側偔偰暆傕戝偒偔偼峀偑傜偢偵嵪傓偺偑155/70ZR13丄庒姳懍搙寁偵僘儗偑弌傞偗偳鉟楉偵傑偲傑偭偰尒偊傞偺偑145/65R13偱丄慜幰偼嵟嬤偺寉帺摦幵偲偟偰偼儗傾僒僀僘側偺偱1杮偺扨壙偼崅傔丄屻幰偼偦傟側傝偵巊梡楌偺偁傞僒僀僘側偺偱偦偙偦偙悢偼偁傞丄偲偄偆偙偲偱偡丅傑偨丄165/65R13偱傕傎傏岆嵎側偟側偺偱偡偑丄偙偪傜偼応崌偵傛偭偰偼僴儞僪儖傪愗偭偨傜慜椫偑偳偭偐偲姳徛偡傞偐傕?偲偄偆寽擮偑偁傞傛偆偱丅偱丄偦傫側拞偱偄偔偮偐栚傪晅偗偨偺偑偁傝傑偟偰丄1偮偼僗僷儖僐偺儊僢僔儏丄1偮偼傾僂僩僗僩儔乕僟Mk8丄1偮偼ENKEI偑愄弌偟偰偨僌儔儀儖梡偺儔儕乕儂僀乕儖丅傫偱丄偦偺拞偱ENKEI偺儔儕乕儂僀乕儖偑偨傑偨傑憲椏崬偱11000墌掱搙偱庤偵擖偭偪傖偭偨偺偱偟偨丅偲偄偆偐丄杮棃5000墌亄憲椏偱嵪傑偣傞偼偢偩偭偨偺偱偡偑丄堄奜偲僶僩儖偵側偭偰偟傑偭偰丄嵟屻偺僟儊墴偟堦敪偱柍棟傗傝棭傔庢傝傑偟偨丅晛抜偼巆傝帪娫3昩偐傜偺擖嶥偱僗僫僀僾棊嶥偽偭偐傝側偺偱丄媣乆偵擖嶥壙奿偺怱棟僶僩儖傪傗傞塇栚偵側偭偰丄偨偭偨5暘偺愴偄偑敄昘傪摜傓傛偆側椻傗娋傕偺偱偟偨丅傑偁尒偨栚偑挻墭偄偭傐偄偺偱撏偄偰偐傜偺偍妝偟傒偱偼偁傞傫偱偡偑丄娫堘偄側偔揾憰偺僸價傪僷僥杽傔偟偰揾傝側偍偝側偄偲偄偗側偄偭傐偄偱偡丅
丂
仜奀奜偺帺嶌僱僘儈庢傝
丂懍搙堘斀庢掲偠傖側偔偰杮暔偺僱僘儈偺曔妉婍偺偙偲偱偡丅
丂奀奜偺庤嶌傝僱僘儈庢傝婍偺摦夋偑偁偭偨偺偱怓乆尒偰偄偨偺偱偡偑丄奆條偁偺庤偙偺庤偱寢峔峫偊傜傟偰偰嬃偒傑偡丅摿偵嬃偄偨巇慻傒偑2庬椶偁傝傑偡丅1偮偼僞僀儔僢僾偲掁傝巺丄岺嬶傪巊偆偲偄偆搝丅僞僀儔僢僾傪備傞備傞偺娐偵偟偰掲傑傞懁傪僄僒偲岺嬶偵宷偄偱偍偒丄僄僒傪偐偠傞偲岺嬶偑棊壓偟偰偦偺廳傒偱僞僀儔僢僾偑掲傑傞偲偄偆傕偺丅摉慠丄僄僒偲僞僀儔僢僾偺嫍棧偼偟傑偭偨帪偵僱僘儈偺摲傗庱傪峣傔傞埵抲偵愝掕偟偰偁傝傑偡丅僞僀儔僢僾傕掁傝巺傕500g偔傜偄偺儌儞僉乕傕偳偙偺偛壠掚偵傕晛捠偵偁傝傑偡偐傜偹偊乮偊丠側偄偭偰丠倵乯丅傑偨丄傕偆1偮偼揤攭傪棙梡偟偨傕偺偱偡丅儁僢僩儃僩儖側偳傪僔乕僜乕忬偵愝抲偟偰偍偒丄僱僘儈偑擖傜側偄忬懺偩偲儁僢僩儃僩儖偺擖岥偼奐偄偰偄傞偗偳丄僱僘儈偑擖偭偰弌岥偐傜弌傛偆偲偟偨傜僔乕僜乕偺尨棟偱儁僢僩儃僩儖偑孹偄偰弌岥偵暻偑弌尰偡傞偲偄偆搝丅偱傕傑偨墱傑偱峴偔偲擖岥偼奐偔丄弌岥偵嬤婑傞偲掲傑傞丅僱僘儈偑曔妉偝傟偨傜儁僢僩儃僩儖偛偲攑婞偟丄傑偨怴偨側儁僢僩儃僩儖偲僄僒傪僙僢僩偡傟偽廔傢傝偲偄偆僗僑偝丅僱僘儈偑儁僢僩儃僩儖偺擖岥傪愽傝敳偗傜傟傞偲偄偆惈幙傪棙梡偟偨傕偺傜偟偄偱偡丅傎偐偵傕僄僒傪庢偭偨傜僐儞僋儕乕僩僽儘僢僋偵墴偟偮傇偝傟傞搝偲偐怓乆偁傝傑偟偨偑丄偳傟傕偙傟傕壠偵偁傞傕偺偱嶌傟傞搝偽偭偐傝偱丄嬃偒偱偟偨丅 |
| VOL932丗暯惉28擭09寧05擔丗偍晽楥偼晐偄偧 |
仜僿儞側嵶嬠姶愼傪怘傜偭偨
丂嬥梛擔丄孭楙峑偑廔傢偭偰偦偺懌偱僕儉偵晽楥偩偗擖傝偵偄偒丄栭偐傜偺柤屆壆峴偵旛偊偰偄傠偄傠弨旛偟偰偄傑偟偨丅傫偱丄側傫偐媫偵僟儖偄側傒偨偄側姶偠偼偁偭偨傫偱偡偑丄斢斞怘偭偰帩偪弌偡僨乕僞椶傪弨旛偟偰憰旛傕梡堄偟偰21帪敿偛傠俫俙倄両偝傫偑寎偊偵棃偨偺偱偦偺傑傑儗僈僔乕偱弌敪丅偦偺帪揰偱婛偵庒姳堘榓姶偑偁偭偨偺偱偡偑丄柤屆壆偵偮偄偨傜塃榬偑柇偵擬偭傐偔丄旾偺愭偑壗偐偵怗傟傞偲柇偵捝偄偺偱偡丅偙偺帪揰偱側傫偐旐抏偟偨側壌丄偭偰婥偯偒傑偟偨丅偪側傒偵擖梺帪揰偱塃傂偠愭偵彫偝側嶤傝彎偑偁偭偨傫偱偡偑丄偳偆傕偙偙偐傜怤擖偟偨柾條丅傑偨丄偙偙偟偽傜偔偢偭偲懱挷偑僀儅僀僠偩偭偨偺傕偁傝丄掞峈椡偑庛偭偰傞偲偙傠偵擔榓尒姶愼偟偨傒偨偄偱偡丅搚梛栭偵側傞偲嶲壛儊儞僶乕偑塃榬偺堎條側庮傟偵婥晅偔儗儀儖偱偟偰丅偲傝偁偊偢擔梛栭偵婣戭偟偰僶僫儞忶堸傫偩傜悘暘儅僔偵側偭偨偺偱崱擔旂晢壢傪庴恌偟偨傜丄側傫偐僗僎乕忬嫷偩偲尵傢傟傑偟偨丅傑偢丄尦乆旾偵偁傞妸枌偲偄偆搝偺挷巕偼椙偔側偐偭偨傒偨偄偱丄妸枌曪墛偲偄偆搝偩偦偆偱偡丅偙傟姰慡偵惍宍奜壢偺暘栰偩傛偹乧乧偲偐巚偭偨傝傕偟偨偺偱偡偑丄傎傫偲偙偺愭惗怓乆抦偭偰偰傃偭偔傝偟傑偡丅尰忬偱傑偢嬝擏慻怐側偳偵偲傝偮偄偨嵶嬠姶愼偺帯椕偑桪愭偵側偭偨偺偱尰嵼搳栻拞偱丄偮偄偱偵帹旲壢傕庴偗偵峴偭偨傜暃旲峯墛偱張曽偝傟偨僯儏乕僉僲儘儞偲1廡娫暪梡偟偰撣傒側偝偄偭偰偙偲偱丄搚梛傑偱條巕尒偵側傝傑偟偨丅
丂
仜柤屆壆墲暅偲幁擏
丂柤屆壆偺掕椺OFF夛偵幁擏傪僗僥乕僉梡偱帩偪偙傕偆偲夋嶔偟偰偄偰乽偍偭偪傖傫丄崱搙攚儘乕僗1杮捀懻傗乿偭偰偍婅偄偡傞揹榖傪偟偨偲偙傠乽僥儊乕偱憕偭嶫偄偰帩偭偰婣傟偲尵偄偨偄偑嬛嫏婜偩偐傜悌偑愝抲偱偗傊傫乿偲尵傢傟偰抐擮丅巇曽偑側偄偺偱旤嶳偺摴偺墂偱從偒擏梡400乮偨傇傫偁傟傕傕擏乯丄幁僒儔儈丄幁僜乕僙乕僕傪阞妉丅偄傗乕丄偙偺娫偺攦偄弌偟偭偰榖偑偙傟側傫偱偡傛丅偦傟傪帩偪偙傫偱僶乕儀僉儏乕偱從偄偰傒偨傫偱偡偑丄偙傟偑傑偨旤枴偄偺側傫偺丅從偒偡偓傞偲屌偔側傞偲偼暦偄偰偨傫偱偡偑丄幚嵺偵偼從偒擏梡偵壓張棟嵪傒偩偭偨偺偱偦偆側傞偙偲傕側偔丄偙傟傑偨椔巘偐傜暦偄偰偄偨偲偍傝偛傑桘偱傕偝傜偵壓張棟傪偟偰偍偄偨偺偱廘傒傕側偔怘偊偰旕忢偵旤枴偱偟偨丅傑偁巰偸傎偳崅偄偺偑寚揰偱偡偑丅傑偨丄恊晝偑傾儂傎偳掁偭偰暥帤捠傝晠傞傎偳椻搥屔偵歑偭偰傞傾儐傪壗偲偐偡傞傋偔戝検偵帩偪崬傫偱傒偨傜奆條寢峔偒傟偄偵怘偭偰偔傟傑偟偰丄偙傫側偙偲傕偁傠偆偐偲帠慜偵庢傝暘偗偰偍偄偨4旵偺傾儐傪巊偄丄栭偛斞梡偵傾儐斞傪悊偄偰傒偨傜偙傟傑偨戝惓夝丅崱夞偼偦傫側偵梡堄偡傞帪娫傕側偐偭偨偺偱僐儊4崌丄傾儐4旵乮墫從偒乯丄僯儞僕儞敿暘乮嵶愗傝乯丄庰丒傒傝傫丒忀桘傪奺戝嶛4丄偙傟偵悈傪懌偟偰捠忢偺悊斞偺悈壛尭偵偟偰億僠両1帪娫屻偵悊偒忋偑偭偨儊僔偼巰偸傎偳旤枴偱偛偞偄傑偟偨丅偁傟偼傕偆偪傚偭偲傾儗儞僕偟偰傑偨暿偵悊偄偰傒傛偆丅婎杮揑偵塃榬偐傜棃傞旝擬偲懱挷偺埆偝偱庰傕偁傑傝堸傔偢僩僪偺傛偆偵彴偵揮偑偭偰傞偙偲傕懡偐偭偨2擔偩偭偨偺偱丄師夞偼傕偦偭偲懱挷傪惍偊偰撍寕偟偨偄偲偙傠偱偡丅
丂
仜壸戜偺愒偄怓偺尨場偺敿暘偼乧乧
丂偙偺娫偪傚偭偲攑僛僢僩偝傫幵懱偺堦晹傪愻偭偰偄偨帪偵乽偁傟丠側傫偐崱堦晹敀偔側傜側偐偭偨偐丠乿偭偰偺偑偁傝傑偟偰丅偱丄傾僆儕傪慡晹壓偟偰偦偺曈偺愒偄偲偙傠偵愻嵻傪朅棫偰偰傇偭偐偗偰10暘曻抲偟偰偐傜婽偺巕偨傢偟偱偛偟偛偟偟偨偲偙傠丄寢峔怓偑棊偪偰峴偒傑偡丅偊丠偊偊偊丠偭偰巚偭偨傫偱偡偑丄傛偔峫偊偨傜攑僛僢僩偝傫偼尦乆愇桘僼傿儔乕傪愊傫偱憱偭偰偄偨幵丅摉慠丄壸戜偵戝検偺愇桘偑偙傏傟偰偄偰傕偍偐偟偔側偔丄偦偺墭傟偑摉慠挋傑偭偰偰傕偍偐偟偔偼側偄偱偡丅偦傟偱偞乕偭偲壸戜堦柺僥僉僩乕偵偁傜偭偰傒偨傜寢峔敀偔側傝傑偟偰丅偲傝偁偊偢崱夞偞偭偔傝愻偭偰傒偰怓乆暘偐偭偨傫偱偡偑丄巚偭偨傎偳彎偼崜偔側偄丄堦斣墯傫偱傞偲偙傠偵偼慜僆乕僫乕偑偪傖傫偲僞僈僱偱寠傪偁偗偰偄偨丄愒偄搝傪偁傞掱搙愻偄棳偟偨傜塉崀傝偺屻偵僒僀僪僇僶乕偵悅傟傞愒偄悈岰偑弌側偔側偭偨丄側偳側偳丅側傫偐恊晝偑庁壠偺憒彍梡偺僨僢僉僽儔僔傪攦偄姺偊傞偲偄偆偺偱丄崱屻怴偟偄僨僢僉僽儔僔偑棃偨傜壸戜傪傕偪傚偭偲鉟楉偵偟偰偐傜嶬棊偲偟偲嵞揾憰傪峫偊偰傒傛偆偲巚偄傑偡丅
丂
仜僨僕僞儖夞楬婎慴偑廔傢偭偨
丂嬥梛擔偱偡偑丄幚偼孭楙峑偺扨尦妋擣僥僗僩偑偁傝傑偟偨丅僨僕僞儖夞楬偺婎慴偲VerilogHDL偺婎慴傪妋擣偡傞僥僗僩偩偭偨偺偱偡偑丄偙偪傜偑巚偭偰偨傛傝偼惗偸傞偄僥僗僩偩偭偨偍偐偘偱84揰庢傞偙偲偑偱偒丄側偐側偐1偐寧栚偼岲僗僞乕僩偑偒傟偨姶偠偱偟偨丅偨偩丄嫲傠偟偄偺偼廡柧偗偐傜偺島媊撪梕偑偄偒側傝傾僙儞僽儔尵岅偵曄傢傞偙偲偱偡丅巚偄偭偒傝嬱偗懌偵傕傎偳偑偁傞傫偱偡偑丄偨偭偨3廡娫庛偺孭楙偱僨僕僞儖夞楬偺婎慴偲HDL傪媗傔崬傒丄偝傜偵4廡娫庛偱傾僙儞僽儔傕墴偟崬傒丄偝傜偵3廡娫傎偳偱C尵岅傪墴偟崬傒丄僨僕僞儖夞楬愝寁偺妋擣帋尡偑HDL偲傾僙儞僽儔偲C傪慻傒崌傢偣偨1枩僇僂儞僞乕嶌惉偭偰偄偆傫偱偡偐傜丄傕偆柍拑嬯拑偟傗偑偭偰偭偰姶偠偱偡丅HDL偵娭偟偰偼愝寁婰弎懁偱枹偩偵帺暘偱偼棟夝偟偒傟偰側偄偲偙傠偑偁傞偺偱丄幚偼妛峑偲摨偠僜僼僩傪僒僽儅僔儞偵僀儞僗僩乕儖偟偰怓乆偲偍曌嫮拞偱偡丅偨偩偙偺僜僼僩丄傾乕僇僀僽揥奐偟偨傜11GB傕HDD怘傜偄偮偔偡僶僇儎儘乕偭傉傝偱偟偰丄偙偺曈壗偲偐偟偰偔傟傛偭偰姶偠偱偡偑丅 |
| VOL931丗暯惉28擭08寧29擔丗尨場偼偍慜偐傛両乮傑偨偐倵 |
仜攑僛僢僩偝傫惍旛怓乆
丂偁傑傝偵傕墭偐偭偨偺偱攑僛僢僩偝傫傪偞乕偭偲愻偭偨傫偱偡偑偁傑傝鉟楉偵側傜偢丄傓偟傠墭偝傪埆壔偝偣偰偟傑偆僪僣儃偵偼傑傝傑偟偨丅偒偭偐偗偼壆崻偐傜棊偪偰偒偨墭傟偱憢僈儔僗偑僔儅僂儅偵側偭偰帺暘偱曫傟偰偟傑偭偨偐傜側偺偱偡偑丄愻偄捈偟偨惃偄偱偮偄偱偵揤堜傪僐儞僷僂儞僪偱堦晹偩偗杹偄偰傒偨偲偙傠丄梊憐奜偵僺僢僇僺僇偵丅偱傕堦晹偩偗僺僇僺僇側偺偼釠偵忈傞偺偱丄1帪娫敿偔傜偄偐偗偰壆崻偩偗慡晹鉟楉偵偟偰傒傑偟偨丅偡傞偲偔偡傫偱偄偨偺偑側傫偐僷偭偲偟偨姶偠偵側偭偰鉟楉偵尒偊傑偟偨丅側偍丄偙偺僐儞僷僂儞僪杹偒偺帪偵敾柧偟偨偺偱偡偑丄偍偱偙晹暘偺B32偱嵁怓偵揾傜傟偰傞偲偙傠丄偁傟僨僇乕儖偱偟偨丅僨僇乕儖側傜偦傝傖乕偔偡傫偱傞傢側偀丄偲偄偆偙偲偱丄偁偦偙偺晹暘偼揾傝捈偝側偔偰傛偝偦偆偱偡丅揾傞偺偼憢偐傜壓偺嵁怓晹暘偩偗偱嵪傒偦偆偱偟偨丅側偍丄偮偄偱偭偪傖乕側傫側傫偱偡偑丄婥偵側偭偨偺偱彮偟偢偮幵撪愻忩傕傗偭偰偭偰傑偡丅側傫偣擾懞偱巊傢傟偰偨偺偱曅偭抂偐傜搚毢偩傜偗側傫偱偡傛丅偦傟傪栄懌偺嵶偐偄僽儔僔偲愻嵻偱嶤偭偰愻偭偰怈偄偰傪孞傝曉偟偰傞傫偱偡偑丄幚嵺傗偭偰傒傞偲偙傟傑偨偔偡傫偱偄偨撪憰偑寢峔傁偭偲偡傞傫偱偡傛偹乕丅傑偁偳偙傑偱傗傞偐偼傾儗偱偡偑丄傕偆偪傚偭偲鉟楉偵偟偰偄偙偆偲巚偄傑偡丅
丂
丂偪側傒偵攑僛僢僩偝傫惍旛偹偨偼傕偆1偮偁傝傑偟偰丄偙偪傜偼僆僀儖娭楢丅傑偢僄儞僕儞偱偡偑丄憱峴嫍棧偑125,000噏偵払偟偰慜僆乕僫乕偭偰偐偔傑偔傑傫偑僆僀儖岎姺偟偰偐傜3000噏憱傝傑偟偨偺偱岎姺偟傑偟偨丅側偍丄慜夞擖傟偰偄偨僆僀儖偼僗僶儖僨傿乕儔乕偺弮惓壔妛崌惉偺10W-40偩偭偨傛偆偱偡偑丄崱夞偼僶僀僋壆偱巐椫梡偲偟偰忢旛偟偰偁傞MOTUL偺巐椫梡H-TECH偺10W-30偱偡丅幚偼3.1L擖傞偲巚偭偰3L撍偭崬傫偱偟傑偭偨偺偱偡偑丄幚嵺偼偳偆傗傜2.8L偺傛偆偱偟偨丅傑偁懡彮枅夞尭偭偰傞傛偆側偺偱偙傟偱條巕尒偱偡丅傑偨丄儈僢僔儑儞傕幚偼僆僀儖岎姺偟偰偄傑偡丅儈僢僔儑儞愊傒懼偊偨帪偵怴偟偄僆僀儖擖傟偨傫偪傖偆傫偐偄偭偰榖偑偁傞傫偱偡偑丄埲慜偐傜寽埬偵偟偰偄偨儈僢僔儑儞偺擖傝偯傜偝偑偳偆傕僆僀儖偵偁傞偺偱偼丠偲偄偆榖偵側偭偨偐傜偱偡丅100宯傗200宯僴僀僛僢僩偼摨偠僩儔儞僗儈僢僔儑儞側傫偱偡偑丄弮惓僆僀儖偺巜掕偑75W-80/GL-3偲偄偆巜掕側偺偱偡偑丄崱擖偭偰傞僩儓僞偺弮惓儈僢僔儑儞僆僀儖偺僌儗乕僪傪挷傋傞偲85W-90/GL-3偲偄偆傕偺偱偟偨丅GL-3偼崌偭偰傑偡偑擲惈偑崅偡偓傑偡丅儈僢僔儑儞偼嶶乆儚僀儎乕傗儗僶乕儅僂儞僩傪偄偠偔偭偨傢偗偱偡偑丄寢嬊栆弸擔偑懕偄偰婥壏偑28搙傪壓夞傜側偔側傝丄塣梡偟偨屻偺儈僢僔儑儞僆僀儖壏搙偑35搙傪壓夞傜側偔側偭偰傗偭偲偙偝僊傾偑僗僐僗僐擖傞傛偆偵側偭偨巒枛丅偙偺偙偲傪巐椫惍旛巑側拠娫偲榖偟偰偄傞偲乽儈僢僔儑儞僆僀儖偺擲惈傪巜掕擲搙偵偟偨傜捈傞傫偪傖偆丠乿偲偄偆榖偑弌偨偺偱幚巤偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅
丂
丂傫偱傕偭偰杮擔丄惍旛梊栺傪擖傟偰偨偺偱儈僢僔儑儞僆僀儖傪岎姺偟偰偒傑偟偨丅晛捠儈僢僔儑儞僆僀儖偺岎姺側傫偰10暘傕偁傝傖乕廔傢傞偲巚偭偨偵丄40暘偨偭偰傕岺応偐傜弌偰偙側偄偺偱偁傟偭偰巚偭偨傜丄岎姺攚宨傪塩嬈偵揱偊偰偄偨偍偐偘偱儈僢僔儑儞儚僀儎乕偺嵞挷惍偑幚巤偝傟偰偍傝丄偝傜偵壓夞傝傕慡晹鉟楉偵僗僠乕儉愻忩偟偰偔傟偰偄傑偟偨丅傑偨丄僄儞僕儞娭學偵偮偄偰僆儌儔僔偟偰傞応強偑偨傇傫僼儘儞僩僔儍僼僩僔乕儖偱師偺幵専傑偱偼帩偮傫偠傖側偄偭偰榖偲偐傕偟偰偔傟傑偟偨丅偱丄岎姺屻偱偡偑丄僆僀儖偑椻偊偰傞忬懺偵傕偐偐傢傜偢僗僢僐僗僐偵僠僃儞僕偱偒傑偡丅崱傑偱僟僽儖僋儔僢僠偩偭偨傝僞僀儈儞僌尒寁傜偭偰偺憖嶌偩偭偨傝偟偰偨偺偑壗偩偭偨傫偩偭偰偔傜偄愨岲挷偱偡丅偆乕傫丄偙傫側偪傚偭偲偟偨擲惈偱曄傢傞傫偩側偀偭偰偍傕偭偰偄偨偲偙傠偱偡偑丄幚嵺儈僢僔儑儞帺懱偑晛捠幵傛傝彫偝偔姷惈廳検偑彫偝偄偨傔丄僋儔僢僠僇僢僩偱慜屻偺夞揮悢嵎偺敪惗偑戝偒偔側偭偰僔儞僋儘儊僢僔儏偑僇僶乕偟偒傟側偔側傞偺偑尨場偺傛偆偱偡丅傑偨丄僴僀僛僢僩偺儈僢僔儑儞偼摉慠忢帪浧崌宆偺僼儖僔儞僋儘偱偡偑丄僔儞僋儘偱崌傢偣傞偙偲傪慜採偺愝寁側偺偱丄僔儞僋儘偑媧廂偟偒傟側偗傟偽偙偆側傞偭偰摉慠偱偡丅偙傟偱傑偨1偮惍旛応偺寽埬偑徚偊傑偟偨丅慜偵愊傫偱偨儈僢僔儑儞傛傝偼傞偐偵惷偐偱徫偭偪傖偄傑偡偑丅
丂
仜Verilog HDL
丂孭楙峑偺孭楙偑IC傪巊偭偨僨僕僞儖夞楬偐傜Verilog HDL偲偄偆僴乕僪僂僃傾婰弎尵岅偵堏偭偰偒偰偄傑偡丅幚嵺偺偲偙傠丄IC夞楬偲HDL傪偨偭偨4廡懌傜偢偱慡晹傗偭偰偟傑偆偭偰憡摉媗傔崬傒側傫偩傛丄偲偼偄偭偟傚偵孭楙傪庴偗偰偄傞朸儖仜僒僗偑帠嬈強偛偲偁傏乕傫偝傟偪傖偭偰孭楙峑偵棃偰傞摨婜惗偺屼尵梩丅尦杮怑偩偗偵傢偐傜側偄偙偲偼寢峔挌擩偵嫵偊偰偔傟傑偡丅偱丄HDL偭偰壗偐偲偄偆偲丄FPGA偲偄偆搝偺拞偵媗傑偭偰傞IC僠僢僾傪慻傒崌傢偣偰夞楬傪惗傒弌偡偨傔偺婰弎尵岅偱偡丅偞偭偔傝C尵岅偵嬤偄峔惉側傫偱偡偑丄if偺偁偲偺end偑徣棯偱偒傞偲偐丄偁偄傑偄偵彂偄偨傜僄儔乕偵側傞偲偐丄偦偺曈偼嵎偑偁傝傑偡丅幚偼懡偔偺慻傒崬傒宆儅僀僐儞側傫偐傕偙偺庤偺HDL偱婰弎偟偰FPGA偱帋嶌偟僥僗僩偟偨偺偵丄FPGA偱偺寢壥傪傕偲偵僇僗僞儉僠僢僾傪嶌偭偨傝偟偰偄傞偦偆偱丄揹巕夞楬媄弍偲偟偰偼抦偭偰偄偨傎偆偑偄偄媄弍傜偟偄偱偡丅偄傗乕丄側偐側偐擄偟偄偱偡傛丅偟偐傕晛捠1偐寧埲忋偐偗偰妎偊傗傞婎慴傪偨偭偨偺8擔偱廔傢傜偣傛偆偭偰偄偆傫偱偡偑丄偦傝傖乕傕偆憡摉偱偡丅偨偩偪傖傫偲摦偄偨帪偺姶摦偼傂偲偟偍偱偡偹乕丅側傫偐崱廡枛偵僥僗僩偑偁傞傜偟偄偺偱偦偙偑偳偆側傞偐僈僋僽儖傕偺偱偼偁傝傑偡偑丅 |
| (C)H28 Takayuki Kazahaya |
   |